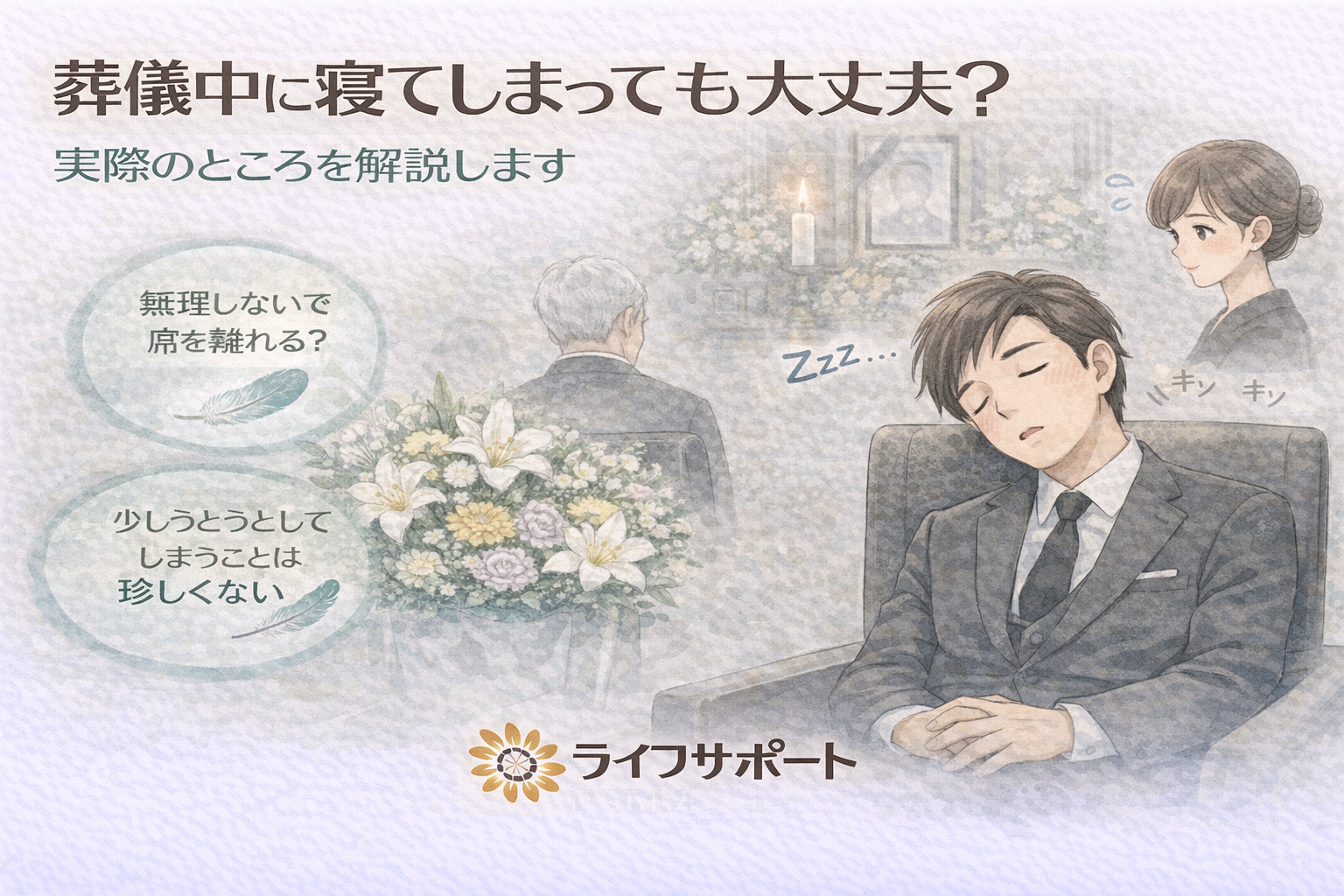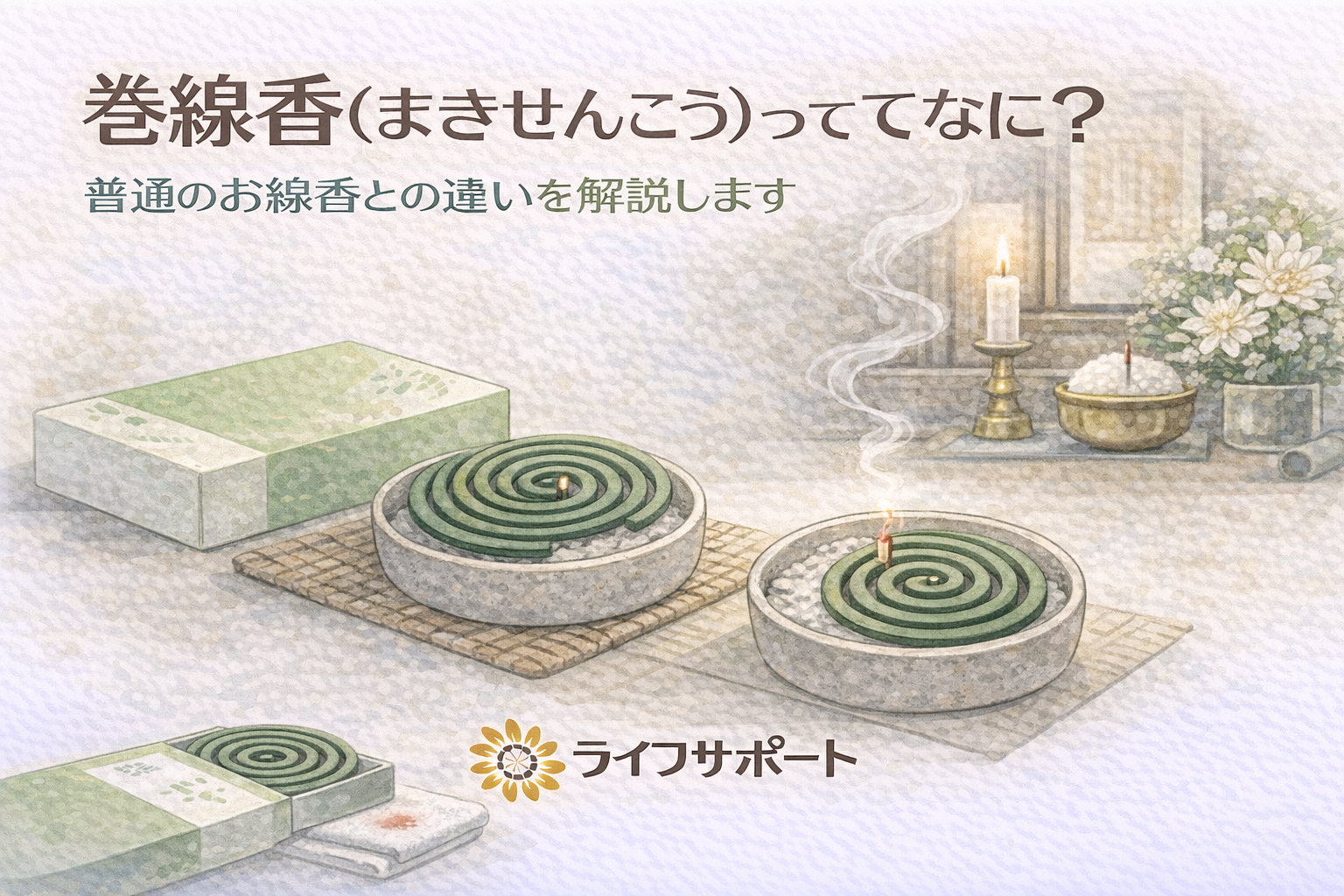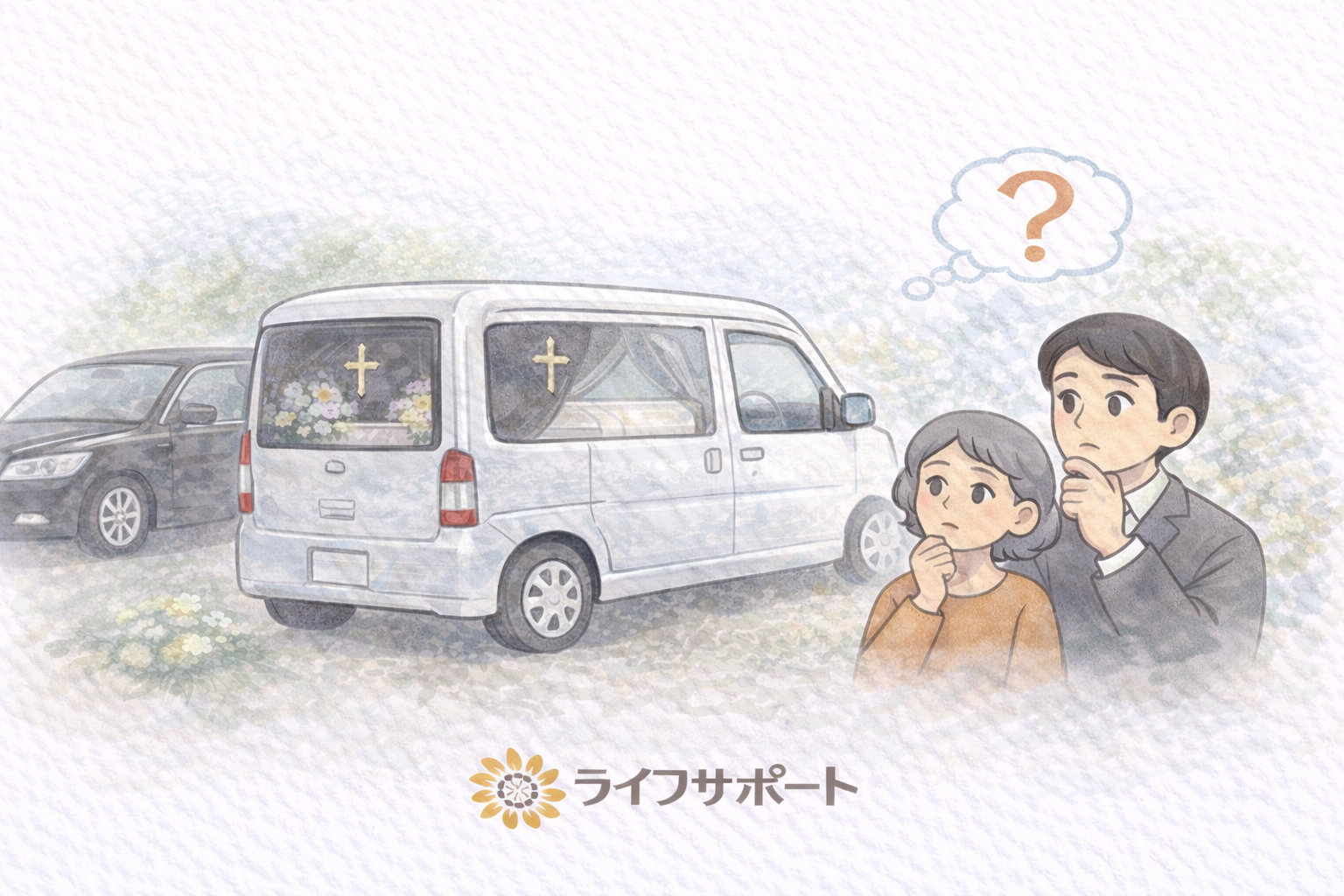「長時間で疲れてしまった…」
「気づいたら少し寝てしまっていた…」
お葬式は、
精神的にも体力的にも負担が大きく、
つい眠くなってしまうことは珍しくありません。
この記事では、
葬儀中に寝てしまった場合、失礼にあたるのかどうかを、
葬儀社の立場から分かりやすくお伝えします。
結論|うとうとしてしまっても、過度に気にしなくて大丈夫です
まず結論からお伝えすると、
体調や状況によって、葬儀中にうとうとしてしまうこと自体は珍しいことではありません。
特に、
- 高齢の方
- 妊娠中の方
- 看病や準備で寝不足の方
- 長時間参列している方
こうした場合は、
眠くなってしまうのも無理はありません。
葬儀は「気持ち」が大切な場です
お葬式は、
- 姿勢を崩さず最後まで起きていること
- 一瞬も目を閉じないこと
が求められる場ではありません。
大切なのは、
故人を思う気持ちがあるかどうかです。
少し目を閉じてしまったからといって、
失礼になることはほとんどありません。
ただし、気をつけたいポイントもあります
一方で、次の点には少し注意しましょう。
- いびきをかくほど熟睡してしまう
- 周囲の方の迷惑になる
- 儀式中に大きく崩れた姿勢になる
こうした場合は、
一度席を外して休むほうが周囲への配慮になります。
無理をせず、離席するのも選択肢です
体調が優れないときは、
- ドアの近くの席に座る
- 途中で静かに退席する
- ロビーや控室で休む
といった対応も問題ありません。
最近のお葬式では、
無理をしない参列が当たり前になってきています。
葬儀社や係の人に一声かけても大丈夫
「少し体調が悪くて…」
そう伝えていただければ、
- 席の移動
- 休める場所の案内
など、対応できることも多くあります。
遠慮せず、周囲に頼ってください。
まとめ|眠くなってしまうのは自然なこと
- 葬儀中にうとうとしてしまうのは珍しくない
- 体調や状況を優先して大丈夫
- 無理な我慢は不要
- 周囲に配慮しながら、休むことも大切
お葬式は、
気持ちを向ける場であって、我慢する場ではありません。
どうか、ご自身の体調も大切にしてください。
ご相談・お問い合わせ
参列中の配慮や、体調が不安な場合の対応についても、
どうぞお気軽にご相談ください。
株式会社ライフサポート
📞 0120-873-444(24時間受付)
🌐 https://anshin-sougi.jp/
ご家族や参列者の状況に合わせて、柔軟にご案内いたします。