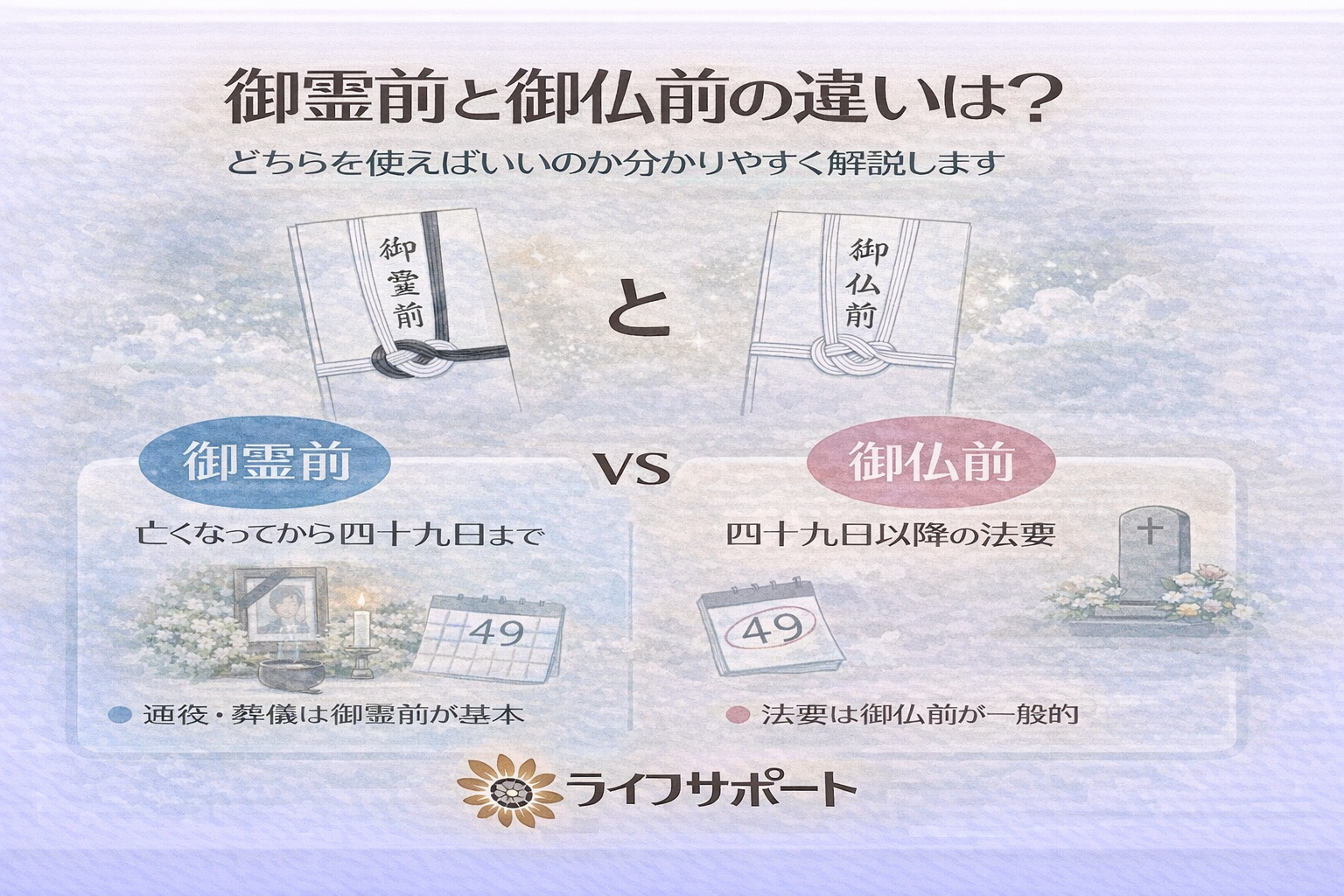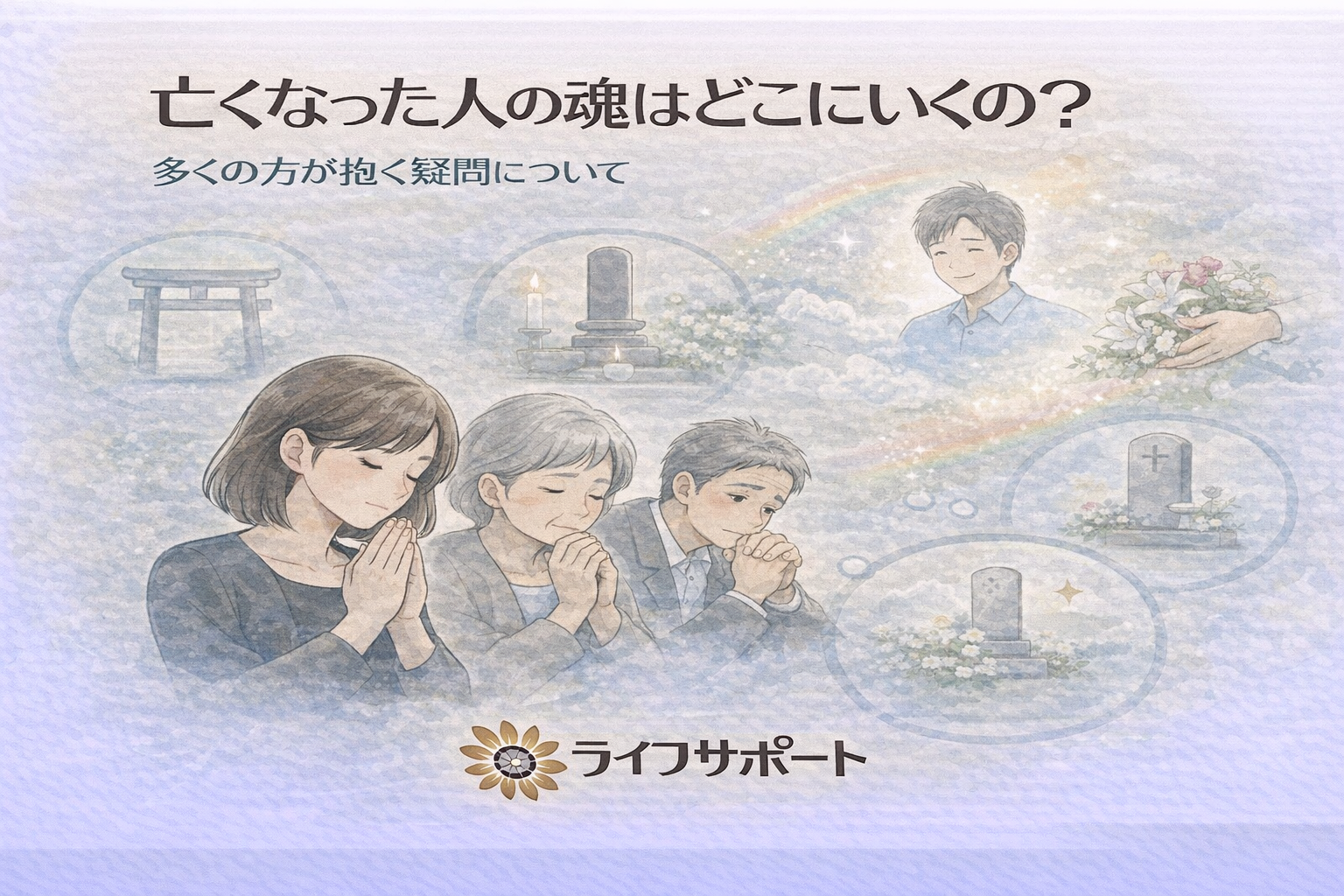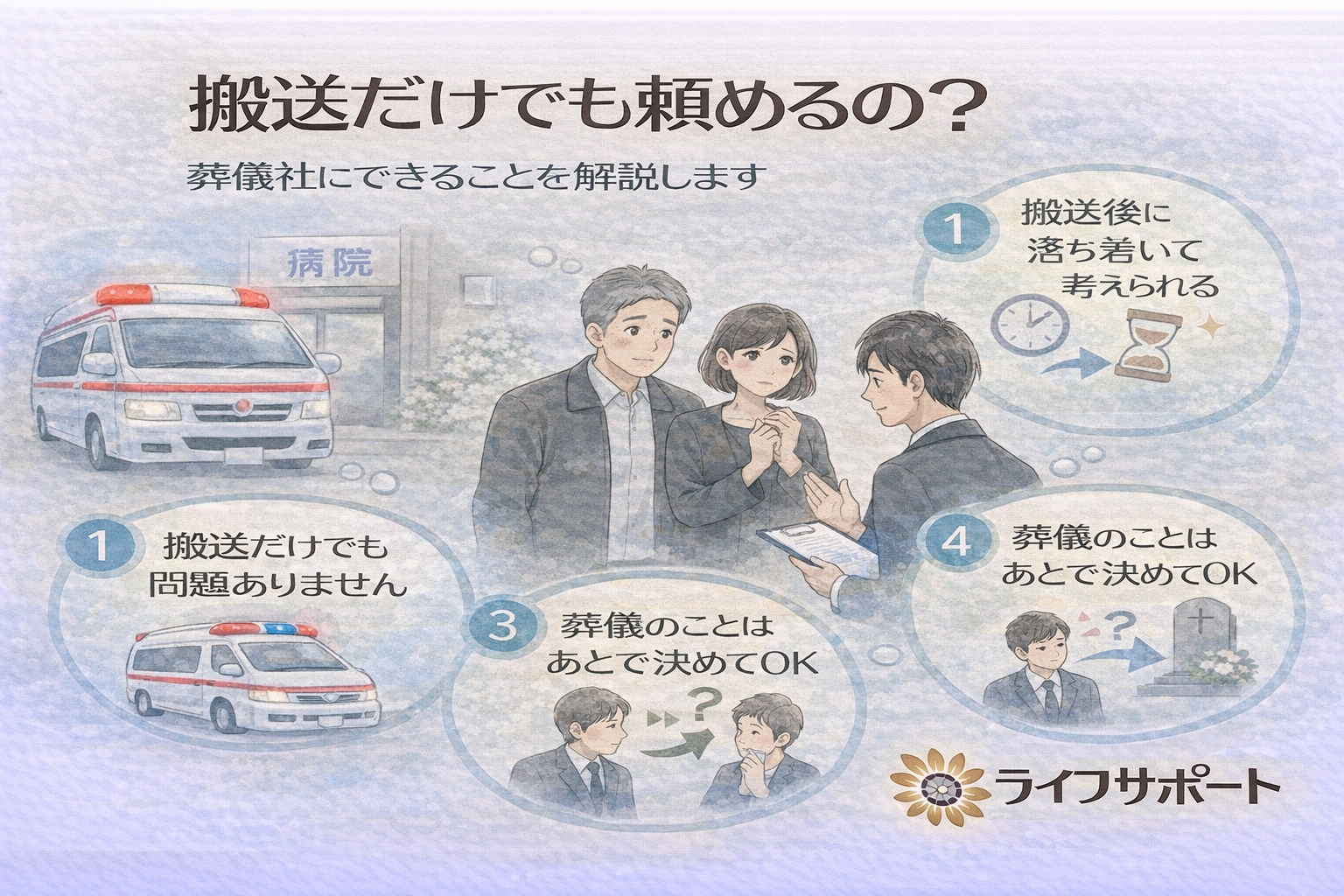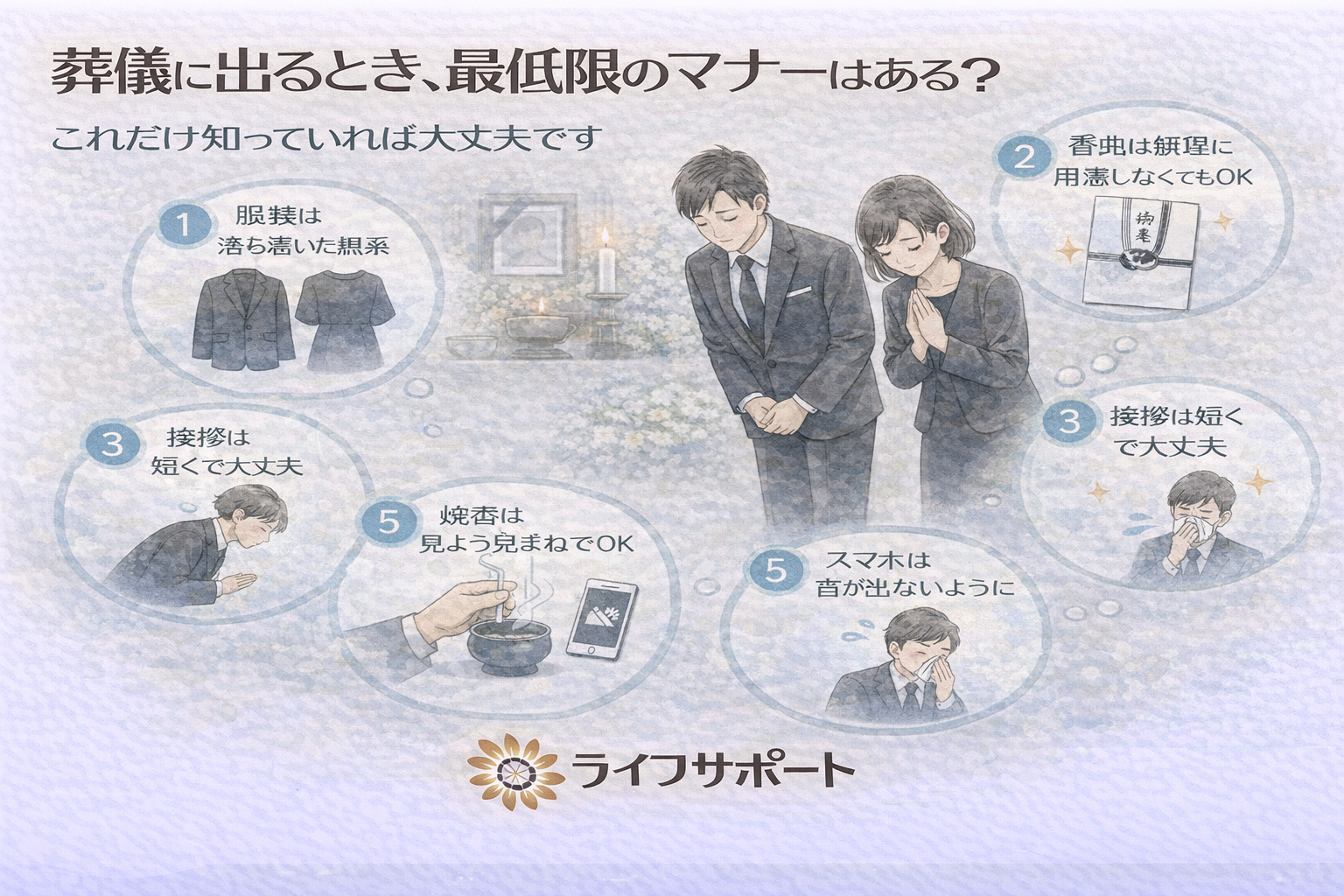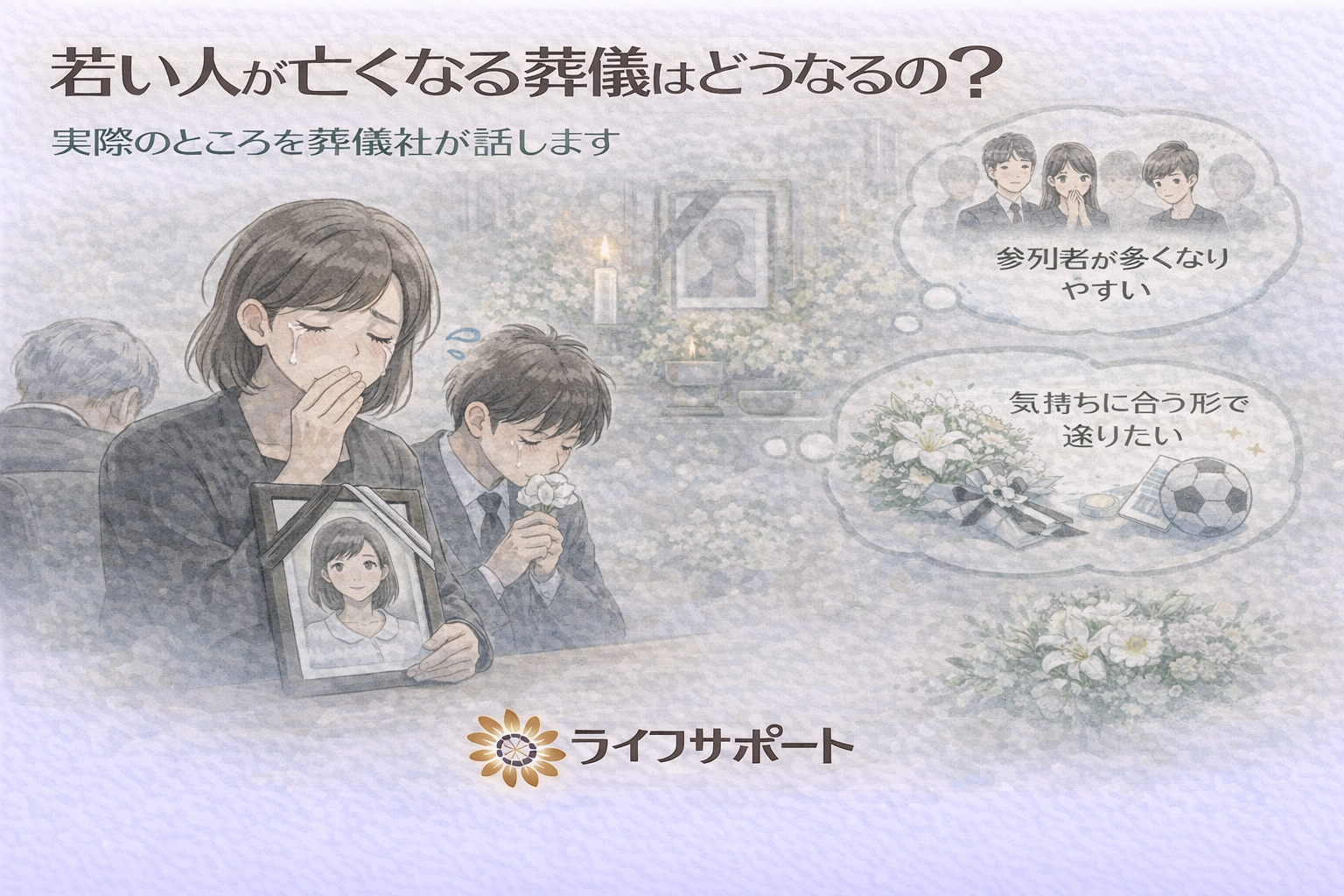御霊前と御仏前の違いは?どちらを使えばいいのか分かりやすく解説します
香典袋を書くときに、
「御霊前?御仏前?」
と手が止まった経験はありませんか?
実際、葬儀の現場でも
とても多い質問のひとつです。
この記事では、
御霊前と御仏前の違い、
そして迷ったときの考え方を、分かりやすく解説します。
結論|基本の違いは「タイミング」です
まず結論からお伝えします。
- 御霊前(ごれいぜん)
→ 亡くなってから、仏になる前 - 御仏前(ごぶつぜん)
→ 仏になったあと
この考え方が基本になります。
御霊前とは?
御霊前は、
亡くなった方の「霊」に対してお供えする、という意味です。
一般的には、
- 通夜
- 葬儀・告別式
- 四十九日より前
で使われることが多い表書きです。
仏教では、亡くなってから四十九日までは
まだ「霊」の状態と考えられています。
御仏前とは?
御仏前は、
仏になられた方へお供えする、という意味になります。
主に、
- 四十九日法要以降
- 一周忌、三回忌などの法要
で使われる表書きです。
ここがややこしい|宗派による違い
実は、宗派によって考え方が少し異なります。
たとえば、
- 浄土真宗
→ 亡くなるとすぐ仏になる、という考え方
→ 通夜・葬儀でも「御仏前」を使うことが多い
ただし、
一般の参列者がそこまで細かく把握するのは難しいですよね。
迷ったときはどうすればいい?
迷った場合は、次の考え方で大丈夫です。
- 通夜・葬儀なら「御霊前」
- 法要なら「御仏前」
これでほとんどのケースは問題ありません。
最近は、
多少表書きが違っても、失礼にあたることはほぼありません。
宗派が分からないときは?
宗派が分からない場合も、
👉 御霊前を選べば無難
と覚えておくと安心です。
実際、葬儀の現場でも
「御霊前」で持参される方が一番多いのが現状です。
葬儀社としてお伝えしたいこと
御霊前・御仏前で悩んでいる方の多くは、
「失礼にならないか」をとても気にされています。
でも大切なのは、
- 形式よりも気持ち
- きちんと弔う心
です。
分からないことがあって当然ですし、
誰も責めることはありません。
まとめ|御霊前と御仏前の違い
- 御霊前:亡くなってから四十九日まで
- 御仏前:四十九日以降の法要
- 通夜・葬儀は御霊前が一般的
- 迷ったら御霊前でOK
ご相談・お問い合わせ
香典や葬儀のマナーについても、
「こんなこと聞いていいのかな?」という内容で大丈夫です。
株式会社ライフサポート
📞 0120-873-444(24時間受付)
🌐 https://anshin-sougi.jp/
状況に合わせて、分かりやすくご案内いたします。