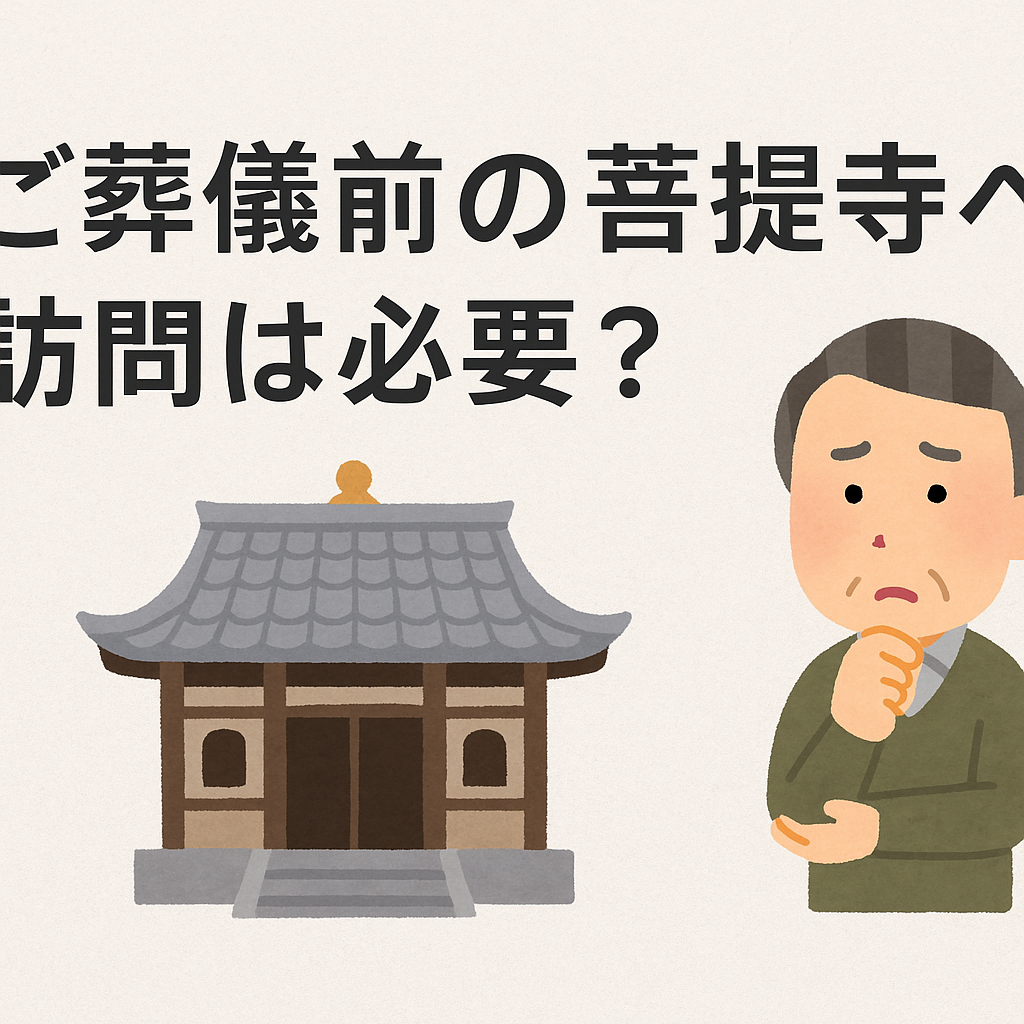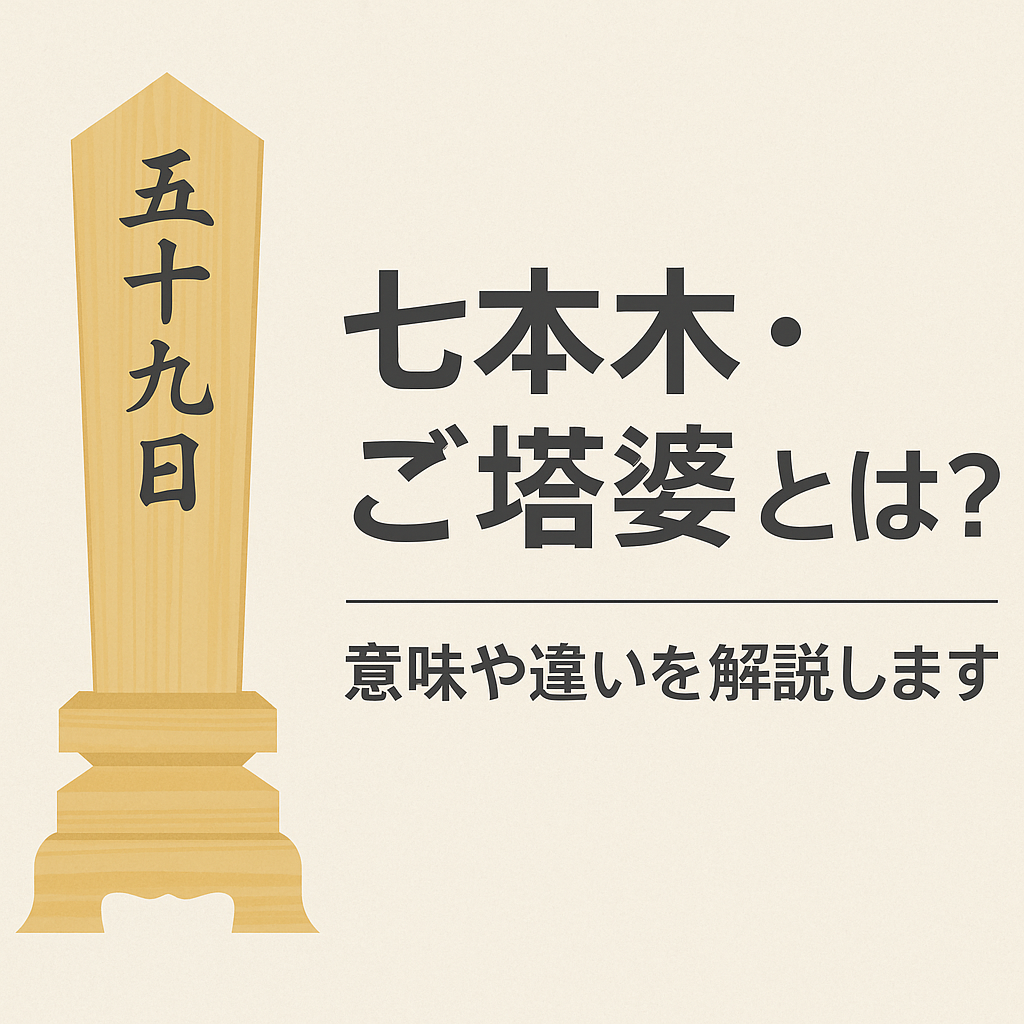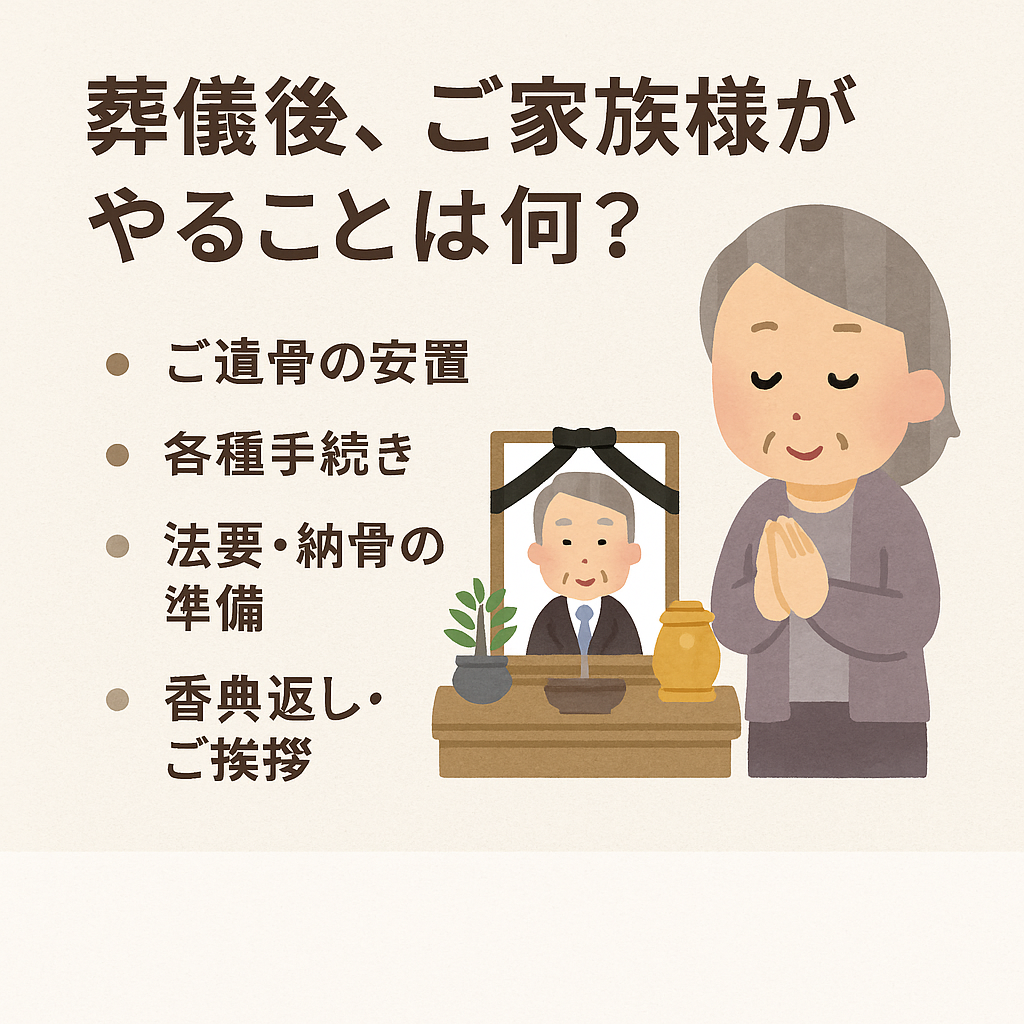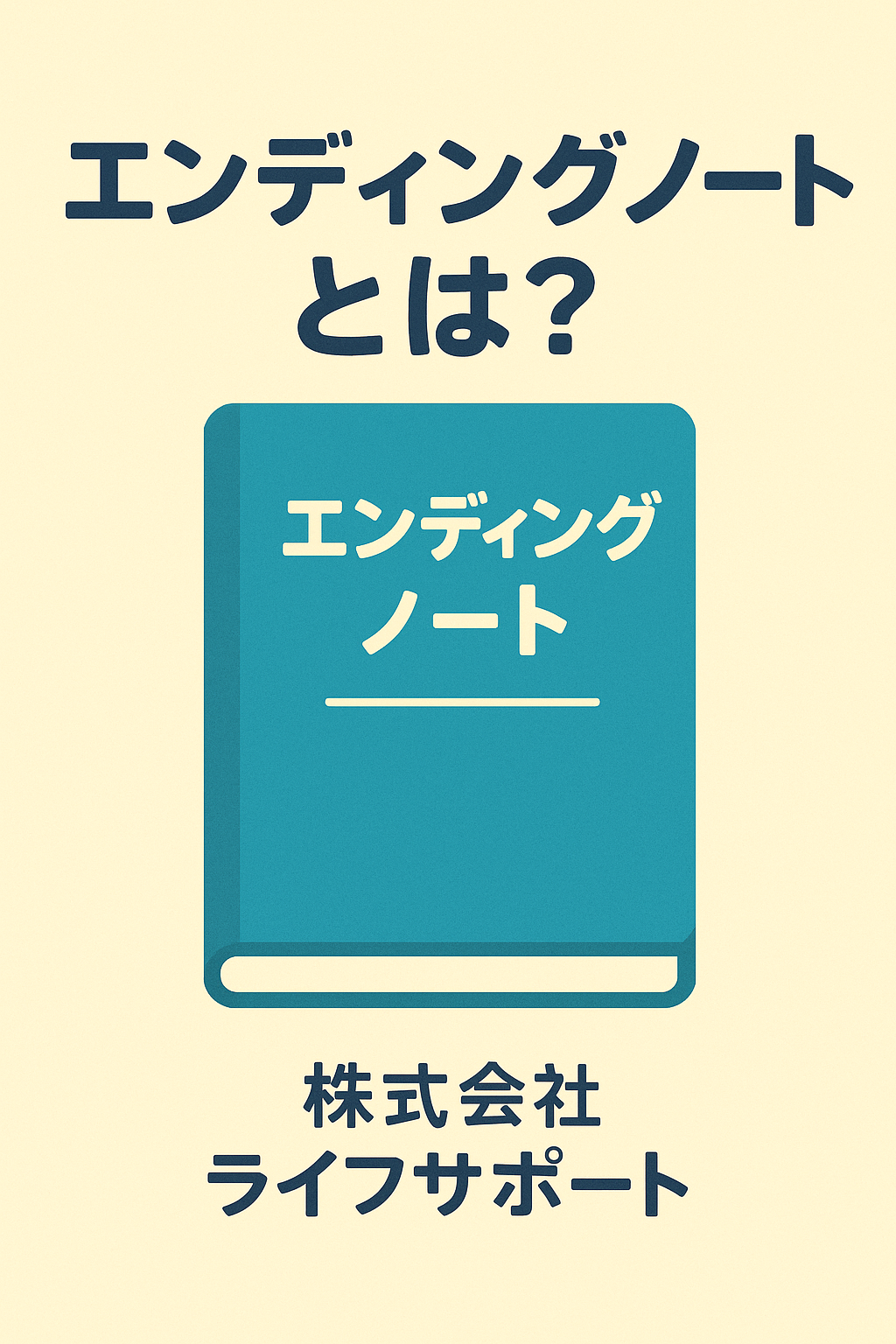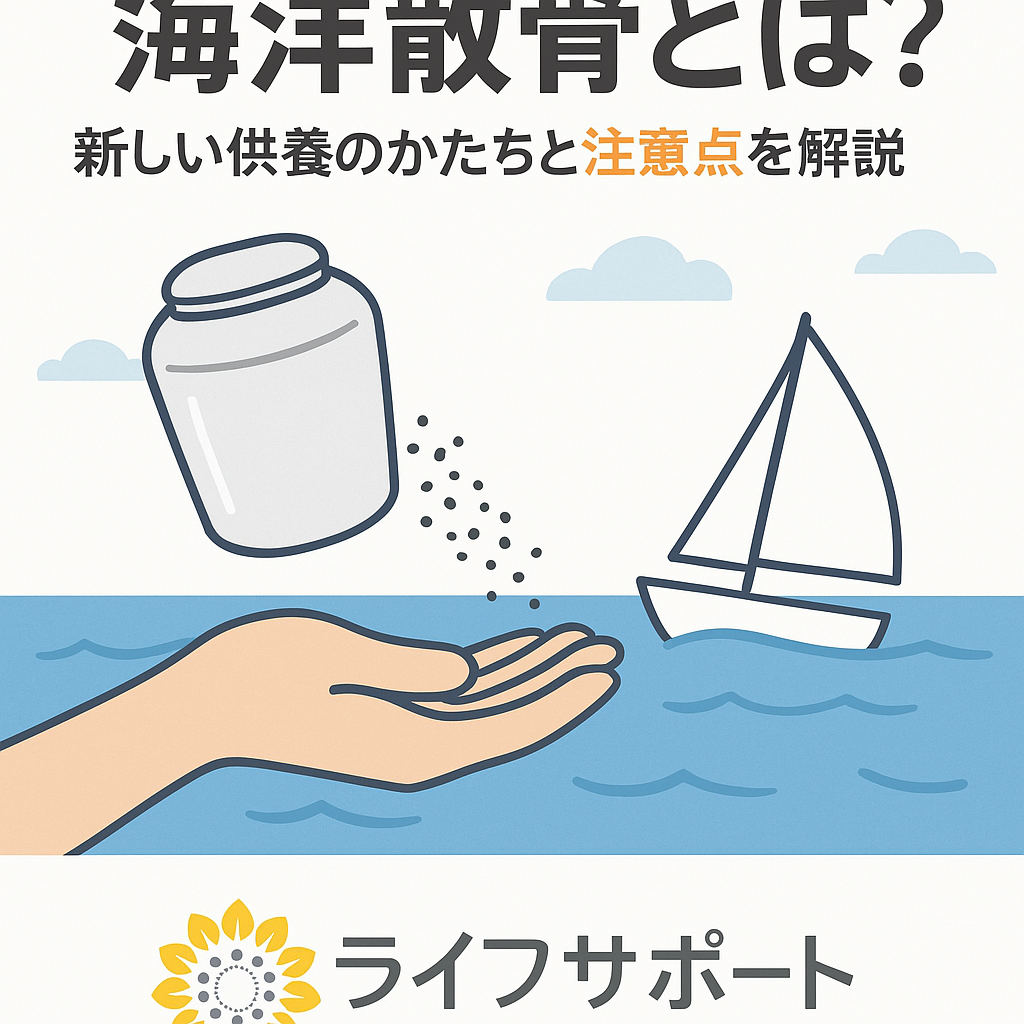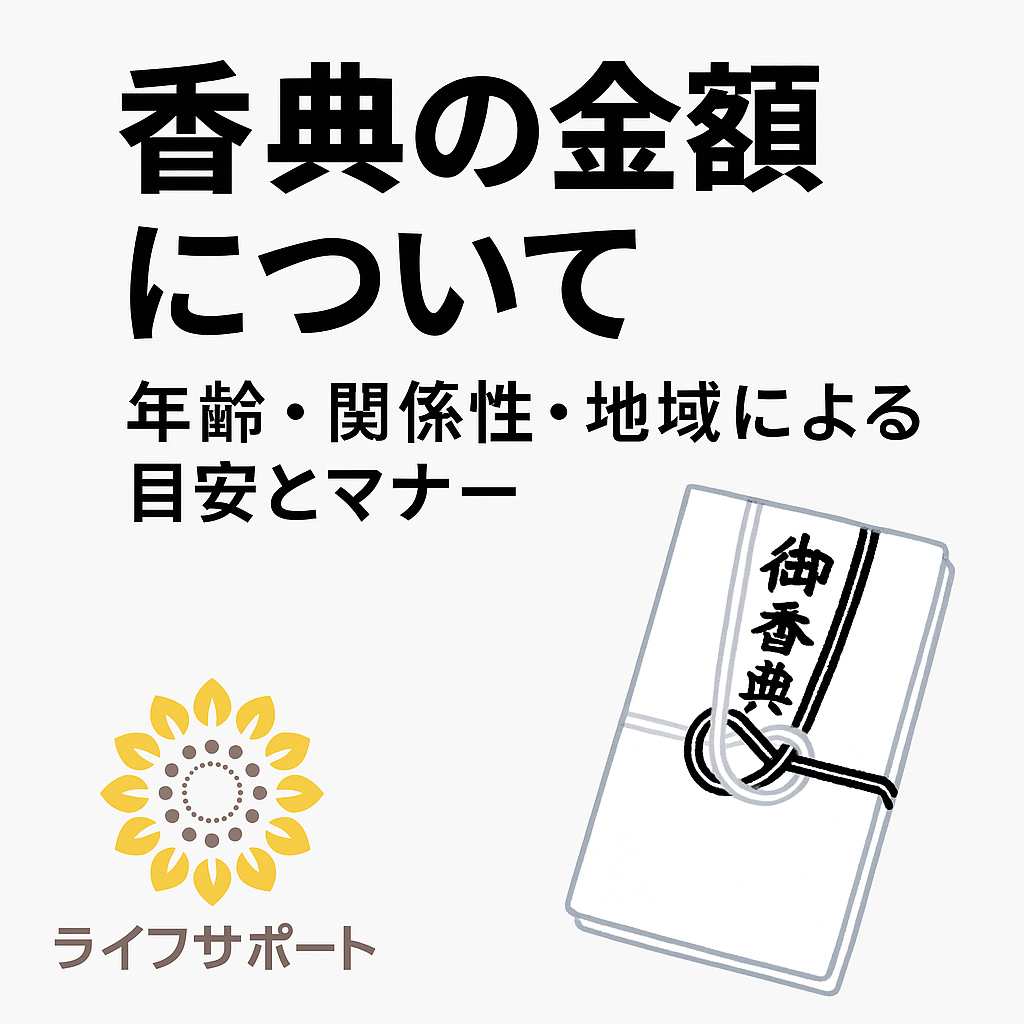日本のご葬儀といえば仏式が大半を占めますが、**天理教(てんりきょう)**は独自の形式で執り行われます。天理教の信者の方のご葬儀に参列することになった際、
「仏式や神道式とどう違うの?」
「焼香やお供えはあるの?」
と迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、天理教のご葬儀の特徴・流れ・参列マナーをわかりやすく解説します。
1. 天理教における「死」の考え方
天理教では、人の死を「亡くなる」というよりも**『出直し(でなおし)』**と表現します。
出直しとは、「人間の魂が一時的に身体を離れ、親神(おやがみ)様のもとへ帰る」という考え方です。
そのため、悲しみに包まれた儀式ではなく、感謝の気持ちで見送る場としてご葬儀(出直しの儀)が行われます。
また、死を「穢れ(けがれ)」とみなすことがないため、仏式で見られる「忌み言葉」や「忌明け」といった考え方はありません。
2. ご葬儀の名称と特徴
天理教のご葬儀は**「出直しの儀」または「葬式のまつり」**と呼ばれます。
僧侶や神職ではなく、天理教の教会長や信者代表が執り行います。
特徴的なポイント
- 焼香は行わず、「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が中心
- お経ではなく、「おつとめ」と呼ばれる鳴物(太鼓・拍子木・三味線など)と歌がある
- **位牌は用いず、「真柱(みはしら)」**と呼ばれる御神体を安置
- 祭壇は神道式に似ており、榊やお供え物を並べる
3. 出直しの儀の流れ(一般例)
- 入場・着席
- 開式のことば
- 祭詞奏上(親神様への感謝を述べる詞)
- おつとめ(鳴物・歌)
- 玉串奉奠(たまぐしを捧げ、拝礼)
- 献饌(けんせん:お供え物をささげる)
- 閉式のことば
※地域や教会の慣習によって、流れが前後することもあります。
4. 香典・服装のマナー
香典の表書き
天理教式では香典を**「御供え」または「御玉串料」**と記します。
仏式の「御香典」は避けましょう。
服装
- 一般の参列者は仏式同様の喪服でOK
- 信者の方は、天理教の正装(はっぴ・たすき)で参列されることもあります。
香典返しや忌明け
- 基本的に香典返しはありません。
- 忌明け法要もなく、**「五十日祭(いそかにちさい)」**が一つの区切りになります。
5. 法要について
天理教では四十九日ではなく、五十日祭が区切りです。
その後は一年祭、三年祭、五年祭…と節目ごとに行われます。
6. 参列時の注意点
- 焼香はないため、玉串奉奠の作法を確認しておくと安心
- お供え物は、果物・野菜・酒などが一般的
- 地域や教会によって細かいしきたりが異なるため、事前に喪家や教会へ確認しましょう。
まとめ
天理教のご葬儀は、仏式や神道式と異なる点が多いですが、
「出直し」という考え方のもと、親神様に感謝し故人を送り出す儀式です。
- 焼香ではなく玉串奉奠
- 位牌ではなく真柱を安置
- 区切りは五十日祭
これらを押さえておけば、安心して参列できます。
👉 地域や教会ごとに違いがあるため、事前の確認が大切です。
当社では天理教式のご葬儀もお手伝いしております。ご不安な方はお気軽にご相談ください。
株式会社ライフサポート
公営斎場での葬儀に特化した専門スタッフがご家族に寄り添います
[0120-873-444](24時間365日受付)
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
株式会社ライフサポート|公営斎場専門の葬儀社(千葉県・茨城県・埼玉県)
大切な「その時」のために、後悔のない準備を。ライフサポートは皆様の安心をお手伝いします。