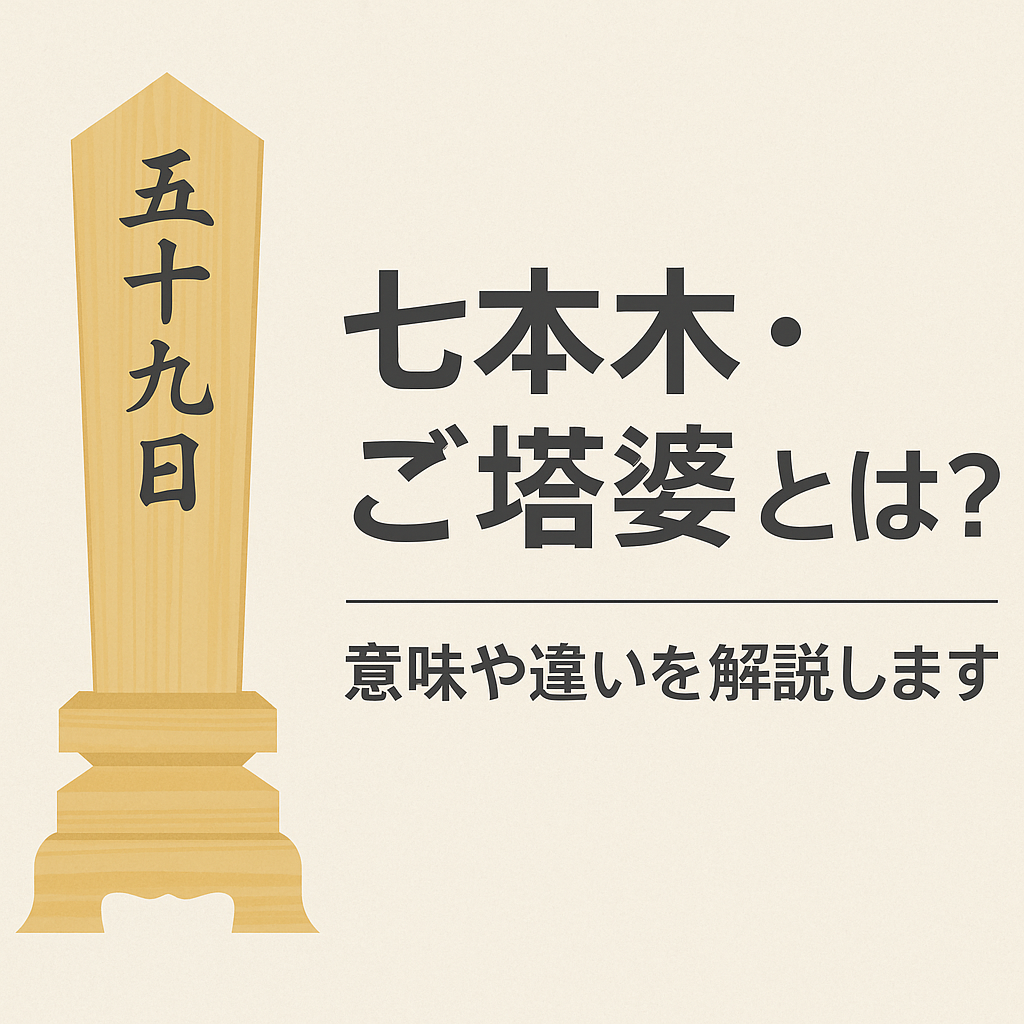葬儀や法要の場でよく目にする「七本木(しちほんぎ)」や「ご塔婆(とうば)」。
でも、「意味はよく知らない」「何のためにあるの?」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、七本木とご塔婆の違いや意味、必要性、いつ用意するものかなどを、わかりやすく解説します。
◆ ご塔婆とは?
「塔婆(とうば)」は、故人の供養のために墓地や法要で立てられる細長い板状の木のことです。
元々は**仏塔(ストゥーパ)**が語源で、「故人の冥福を祈るための供養塔」として立てられます。
▼ご塔婆の特徴
- 材質:主にヒノキや杉など
- 形状:先端が五重塔のような形に加工されている
- 書かれる内容:
- 回忌法要の種別(〇回忌)
- 故人の戒名や俗名
- 施主名
- 日付やお寺の名前など
法要やお墓参りの際にご塔婆を建てることで、故人の功徳を積み、成仏を願う意味があります。
◆ 七本木(しちほんぎ)とは?
「七本木」とは、ご塔婆の一種で、特に四十九日法要(満中陰)で使用される特別な塔婆です。
「七本木」という名前の由来は、文字通り「7本」立てることにあります。
これは、故人が亡くなってから七七日(しちしちにち)、つまり49日間のあいだ、七日ごとに裁きを受けるという仏教の教えに基づいています。
▼七本木の構成
- 初七日から七七日(49日)までの7回の追善供養の塔婆を1本ずつ建てる
- 各塔婆に「初七日」「二七日」…「七七日」と書かれている
- 一般的に四十九日法要の際に、まとめて7本の塔婆を建てて供養する
◆ 七本木と通常のご塔婆の違い
| 項目 | 七本木 | ご塔婆(通常) |
|---|---|---|
| 本数 | 7本まとめて | 1本から数本 |
| 建てる時期 | 四十九日(満中陰)法要 | 回忌法要・納骨・お彼岸など |
| 意味 | 7回の裁きすべてへの供養 | 特定の法要や個別の供養 |
◆ ご塔婆・七本木は必要?いつ誰が建てる?
塔婆供養は仏教の中でも特に浄土宗・真言宗・天台宗・日蓮宗などで行われる習慣です。
曹洞宗や臨済宗など禅宗では塔婆を立てないこともあります(宗派やお寺の方針によります)。
▼誰が建てる?
施主(喪主や遺族)が依頼し、お寺が作成してくれます。
一般的には、塔婆1本あたり数千円〜1万円程度の「塔婆料」が必要です。
◆ まとめ
- 「ご塔婆」は故人の供養のために墓地などに立てる細長い木の板
- 「七本木」は49日法要の際に建てる、初七日から七七日までの7本の塔婆
- 宗派によっては行わないこともあるので、事前にお寺に確認を
ご家族が安心して供養を行えるよう、「ご塔婆」や「七本木」の意味を正しく知っておくことはとても大切です。
葬儀や法要のご不安があれば、ぜひお気軽にライフサポートまでご相談ください。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
株式会社ライフサポート|公営斎場専門の葬儀社(千葉県・茨城県・埼玉県)
大切な「その時」のために、後悔のない準備を。ライフサポートは皆様の安心をお手伝いします。