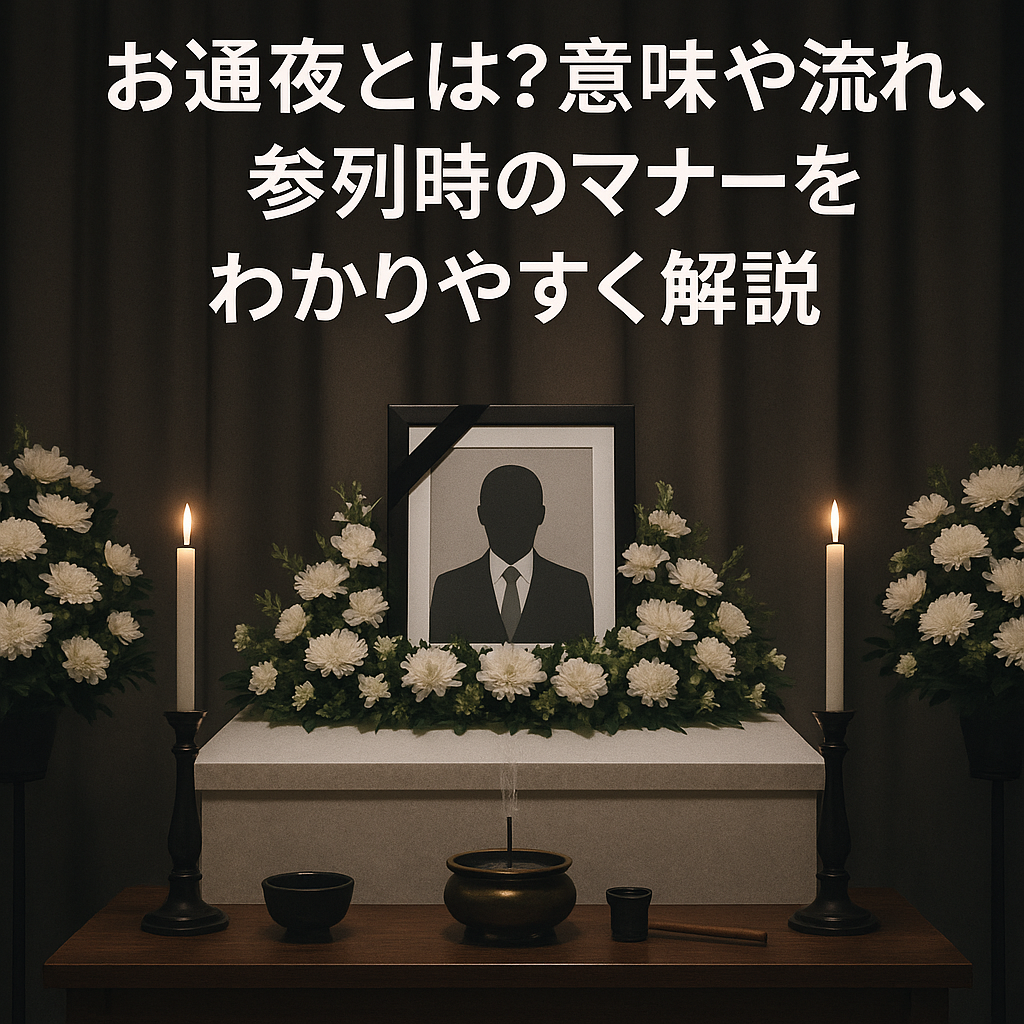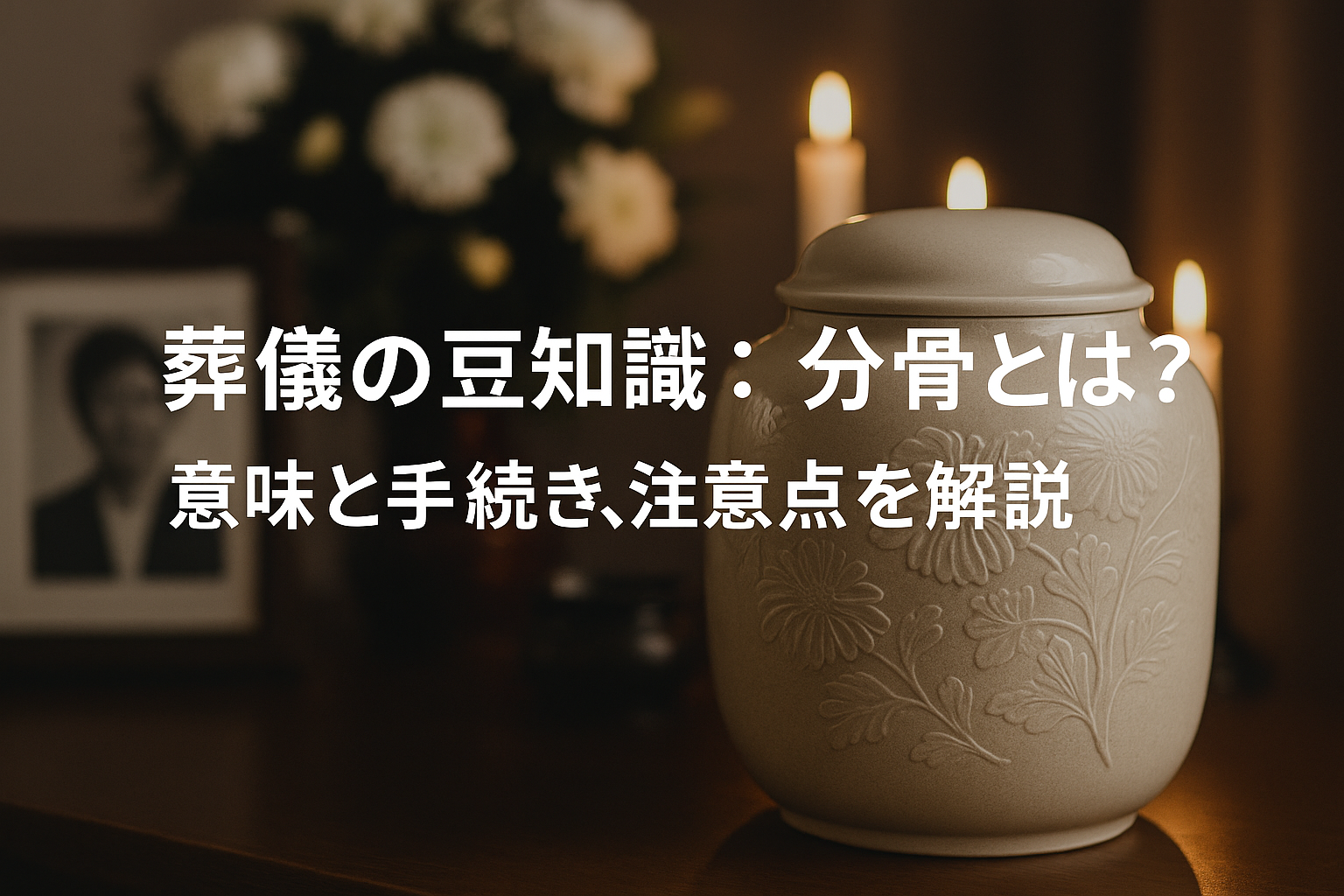葬儀が終わると、ほっとする一方で「この後は何をすればよいのか」と不安に感じるご家族も多いのではないでしょうか。ここでは、葬儀後に必要となる主な手続きや準備について、わかりやすくまとめました。
1. 四十九日法要・納骨の準備
仏式では、葬儀から四十九日までが忌中とされ、この期間を一区切りとします。
- 法要の準備:お寺や僧侶、親族への連絡、会場や会食の手配が必要です。
- 納骨:四十九日の法要に合わせて納骨を行うことが多いため、お墓や納骨堂の準備も同時に進めます。
2. 香典返し(忌明け返礼品)
葬儀の際にいただいたご香典へのお礼として、四十九日頃に「香典返し」をお送りします。
- 相場はいただいた額の半返し程度が目安。
- 品物はタオルや食品、カタログギフトなどが一般的です。
3. 役所関係の手続き
故人様が亡くなられた後は、役所や関係機関への届出が必要です。
- 年金の停止手続き
- 健康保険・介護保険の資格抹消
- 世帯主変更や扶養控除の申請
- 相続に関する諸手続き
これらは期限が定められているものもありますので、早めに確認することが大切です。
4. 相続・遺産整理
葬儀後、避けて通れないのが相続手続きです。
- 預貯金や不動産の名義変更
- 相続税の申告(原則10か月以内)
- 遺言書の有無の確認
複雑な場合は司法書士・税理士など専門家に相談すると安心です。
5. 心のケアと生活の再建
ご家族が大切な方を失った悲しみは簡単には癒えません。
- ご近所や親族との交流を大切にする
- 法要やお墓参りを通して区切りをつける
- 生活リズムを整える
心の整理をしながら、少しずつ日常生活を取り戻していくことが大切です。
まとめ
葬儀後には、法要や納骨の準備、香典返し、役所手続き、相続など、さまざまな対応が必要になります。突然の出来事に追われる中で大変ですが、ひとつずつ順序立てて取り組めば必ず落ち着いて進められます。
ライフサポートでは、葬儀後のご相談や相続サポートも承っております。お気軽にご連絡ください。
📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
株式会社ライフサポート|公営斎場専門の葬儀社(千葉県・茨城県・埼玉県)
大切な「その時」のために、後悔のない準備を。ライフサポートは皆様の安心をお手伝いします。