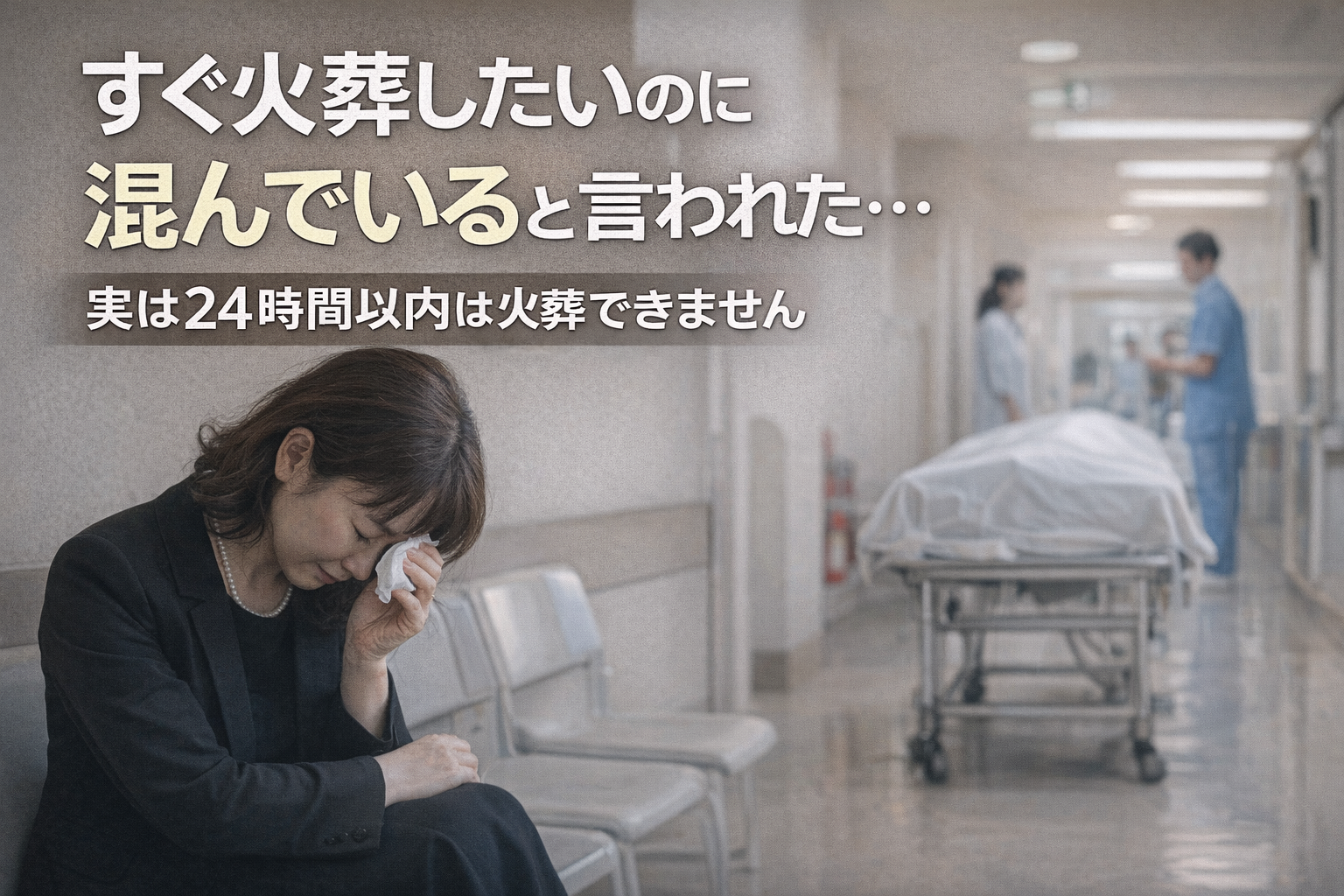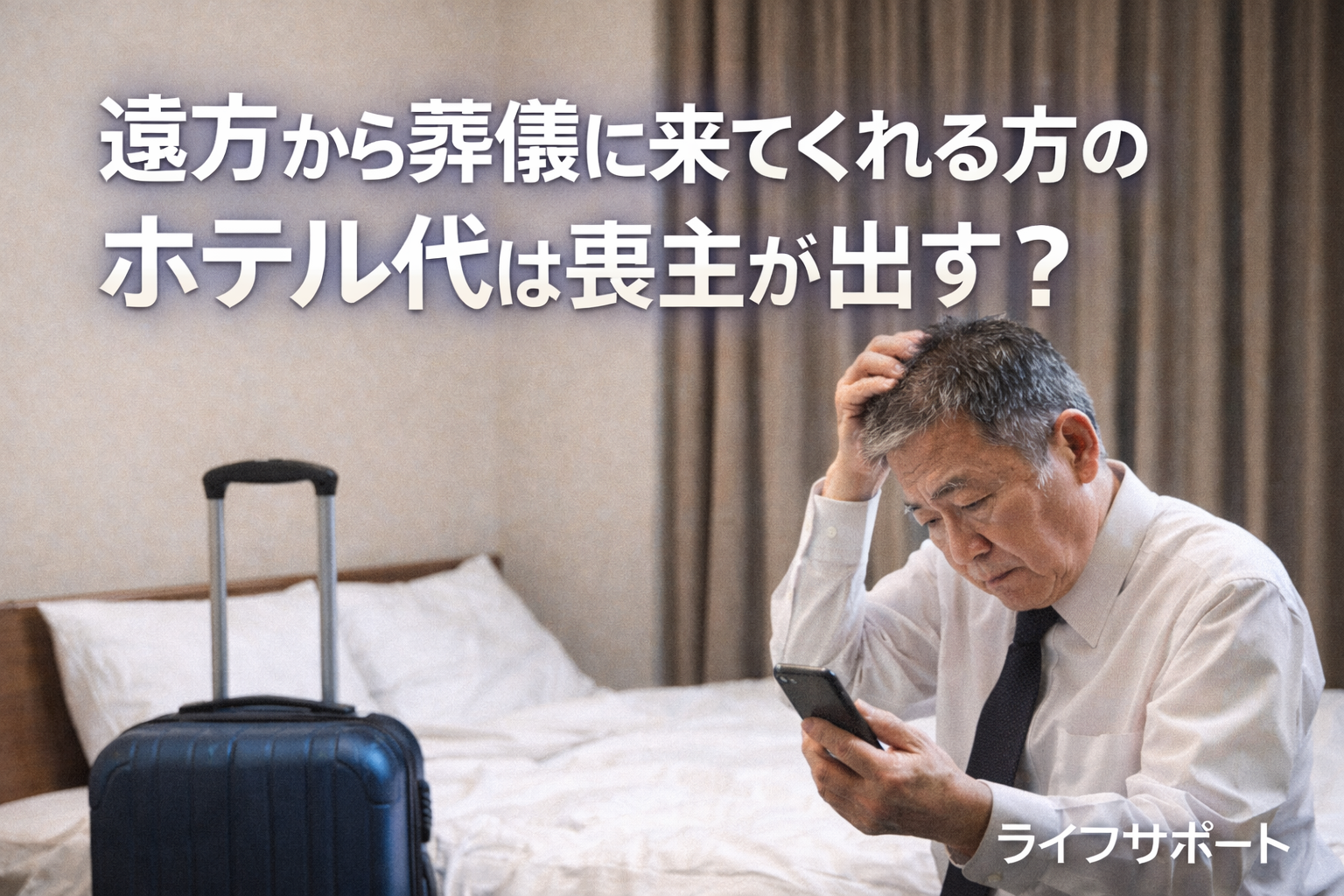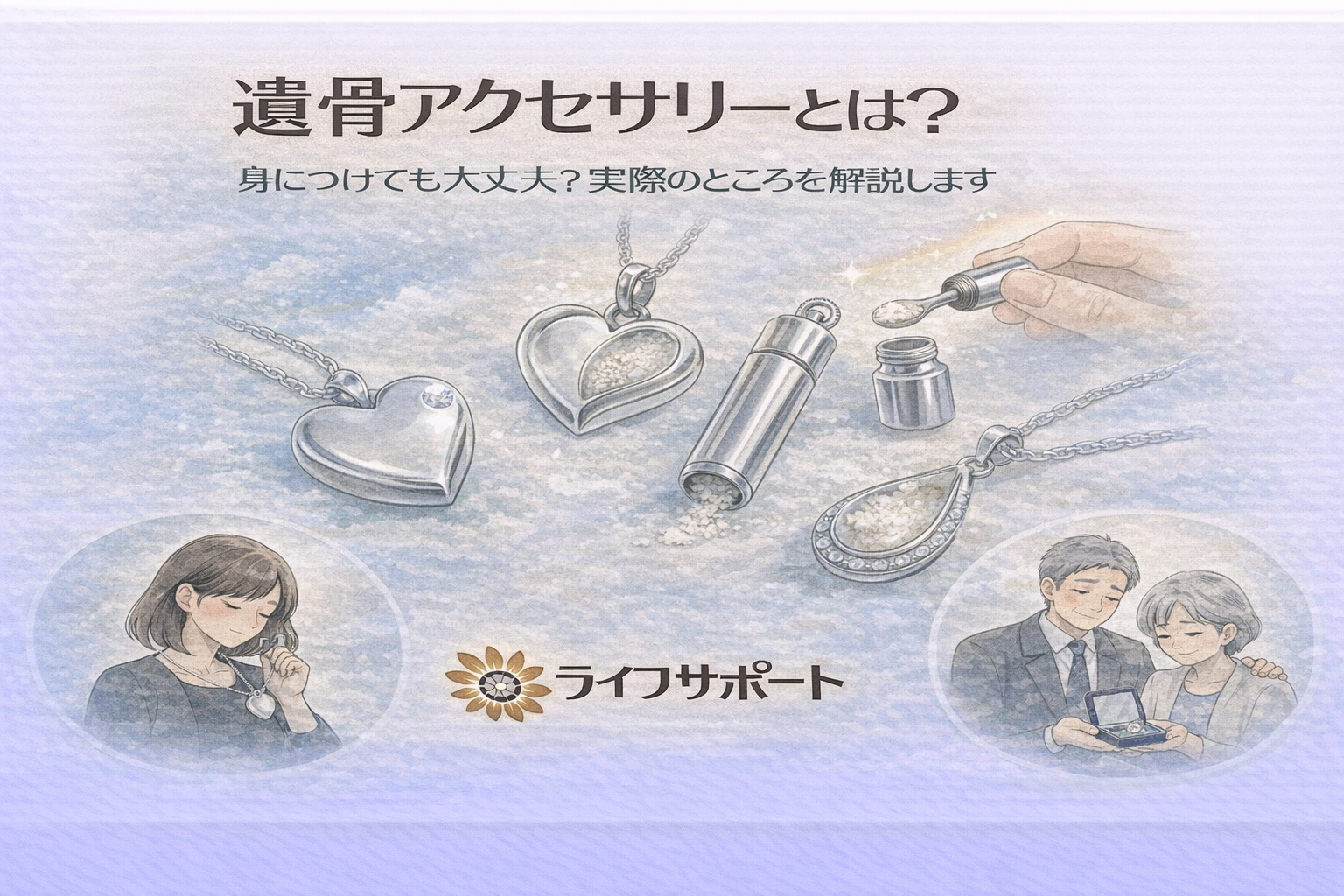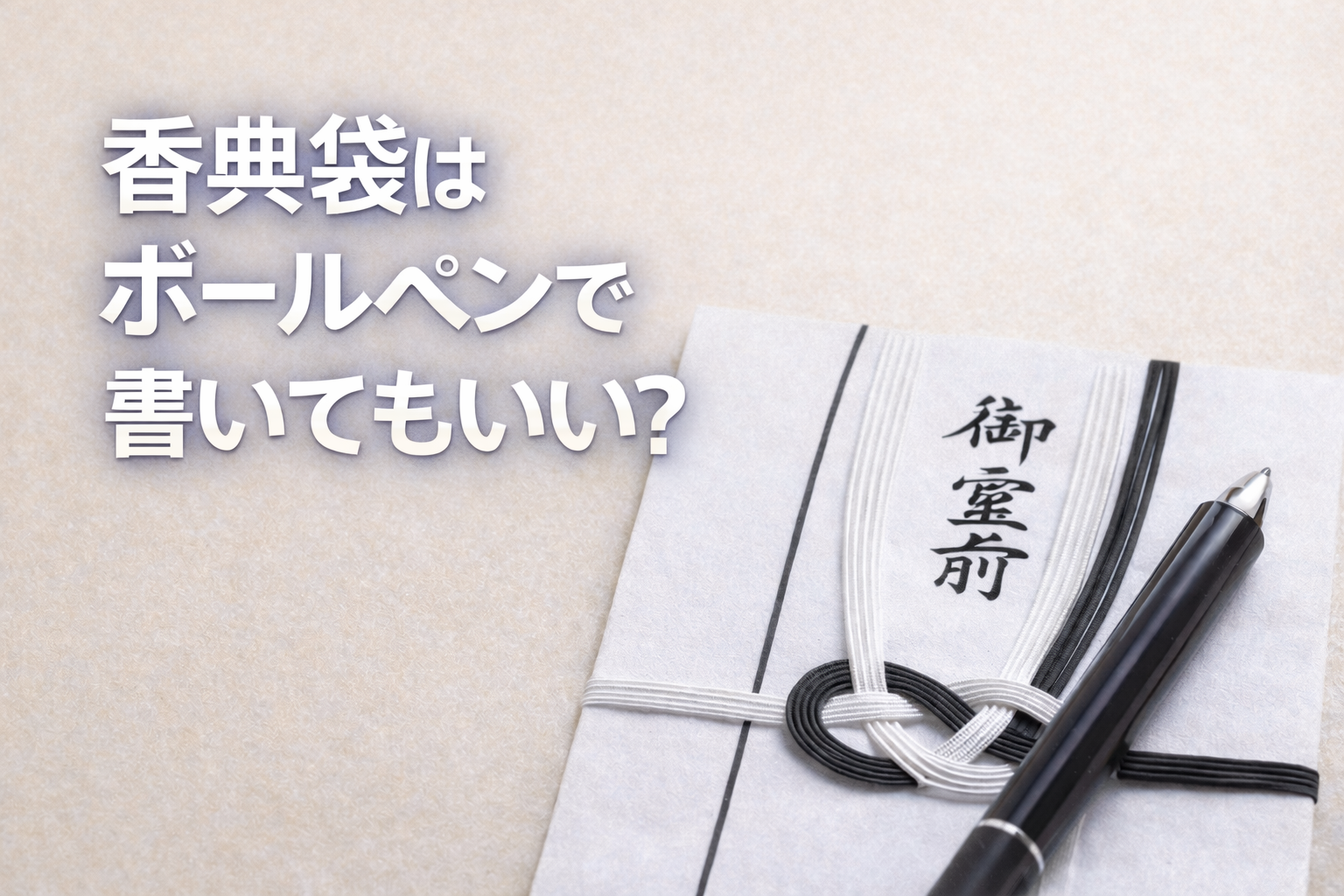葬儀の打ち合わせで、よく聞かれる質問のひとつが
「霊柩車には何人乗れますか?」
というものです。
火葬場までの移動をどうするかは、
当日の流れにも関わる大切なポイントです。
この記事では、
- 霊柩車に乗れる人数の目安
- 車種による違い
- 注意しておきたいポイント
を分かりやすく解説します。
結論|一般的には「1〜2名」が目安
多くの霊柩車は、
👉 運転手+ご遺体の棺
でスペースの大半を使います。
そのため、
同乗できるのは1〜2名程度
が一般的です。
車種によって人数は変わる
① 洋型霊柩車
(昔ながらの装飾があるタイプ)
- 同乗:1名程度
- 場合によっては同乗不可
スペースが限られるため、
人数は少なめです。
② バン型霊柩車(現在主流)
- 同乗:1〜2名
- 後部座席あり
もっとも一般的で、
家族1名が同乗するケースが多いです。
③ ワゴン・ミニバン型
- 同乗:2〜3名可能な場合あり
家族葬などで
複数人が一緒に移動したい場合に使われます。
乗りきれない場合はどうする?
霊柩車に全員は乗れないため、
- 自家用車で移動
- タクシーを手配
- マイクロバスを利用
するケースが一般的です。
特に参列者が多い場合は、
マイクロバスの利用がよく選ばれます。
同乗する人は誰が多い?
一般的には、
- 喪主
- 配偶者
- 近親者1名
など、
もっとも故人に近い方が同乗します。
事前に確認しておきたいポイント
- 霊柩車の車種
- 同乗可能人数
- 火葬場までの移動方法
これらを事前に決めておくと、
当日がスムーズになります。
まとめ|霊柩車は1〜2名が基本
✔ 一般的な同乗人数は1〜2名
✔ 車種により2〜3名可能な場合も
✔ 乗れない人は別移動を手配
✔ 事前確認が大切
「うちの場合は何人乗れる?」
と迷ったら、
葬儀社に確認するのが一番確実です。
ご相談・お問い合わせ
火葬場の見学や、事前相談についても
どうぞお気軽にお問い合わせください。
株式会社ライフサポート
📞 0120-873-444(24時間受付)
🌐 https://anshin-sougi.jp/
状況に合わせて、分かりやすくご案内いたします。