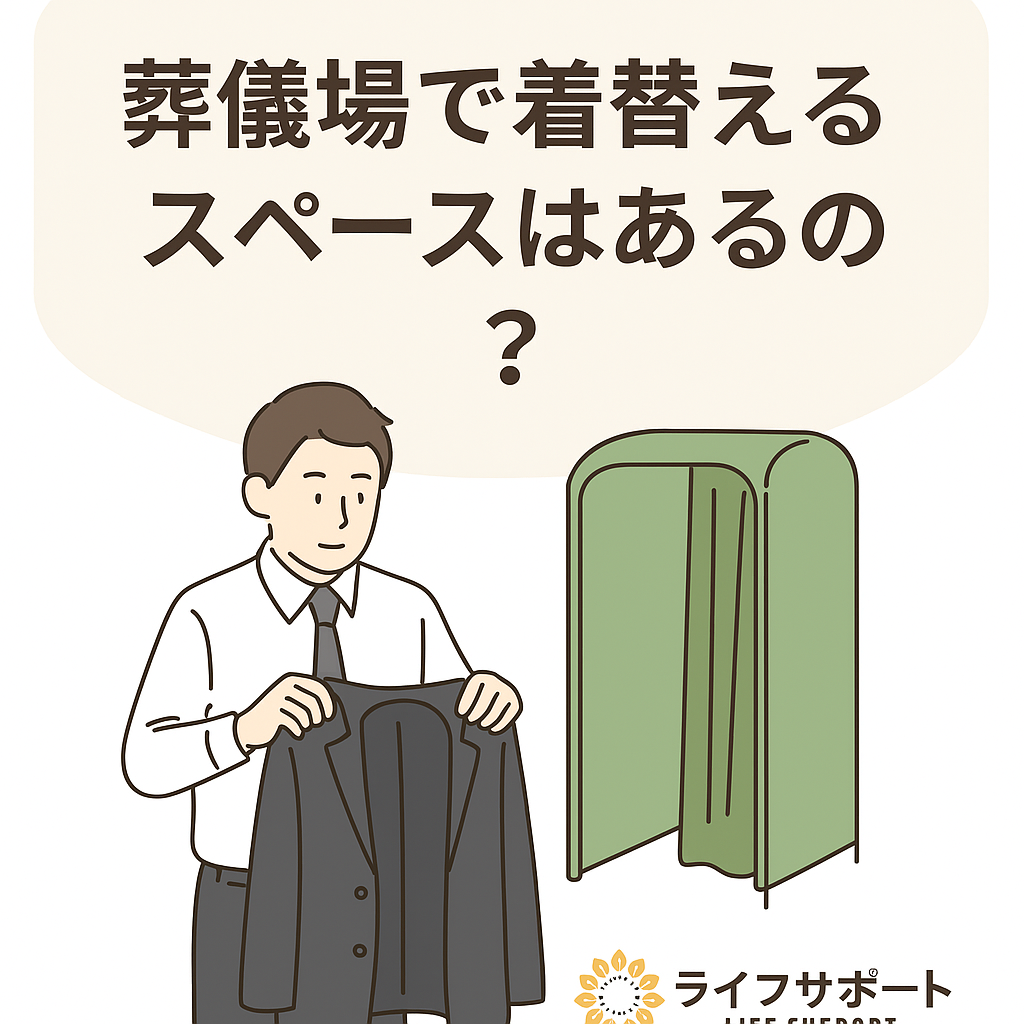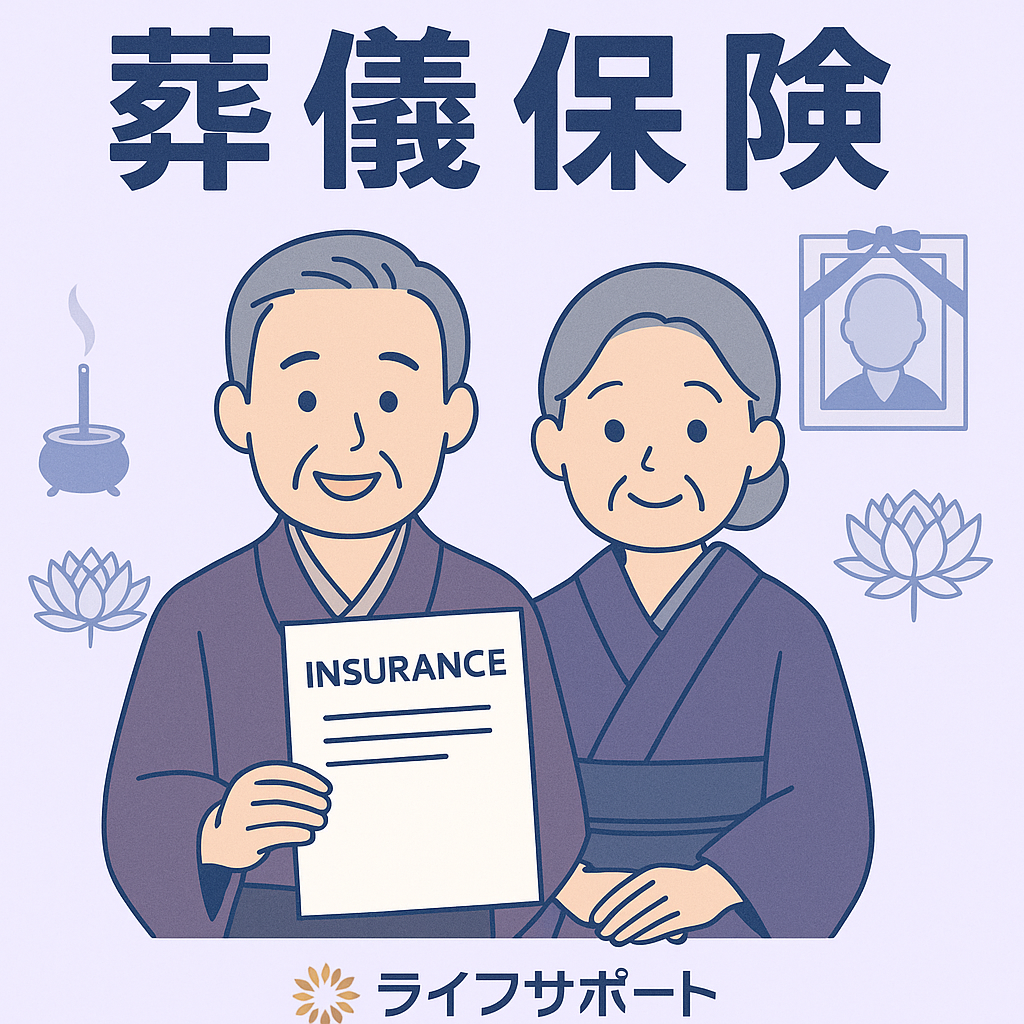企業のトップや功労者が亡くなった際に執り行われる「社葬(しゃそう)」。
一般の葬儀とは異なる形式や目的を持つこの社葬について、今回は葬儀社の立場から詳しくご紹介いたします。
社葬とは?意味と目的
「社葬」とは、会社や団体が主催して執り行う葬儀のことです。
社長・会長・創業者など企業に多大な貢献をした人物の逝去時に、会社としてその功績を称え、社員や取引先、関係者と共に故人を偲ぶ場を設けます。
社葬の目的
- 故人の功績をたたえ、感謝を表す
- 社内外への正式な訃報通知
- 社会的信用や対外的印象の保持・向上
- 社員の喪失感を癒し、団結を促す機会
社葬の種類
社葬には大きく分けて以下の2つの形式があります。
1. 単独社葬
故人の家族とは別に、会社単独で開催する葬儀。
取引先や社員・関係者など、企業ネットワークに向けての公式な場です。
2. 合同葬(合同社葬)
家族葬と社葬を兼ねた形式。
ご遺族の意向と会社の意向を合わせ、1度の式で両者を対応するスタイルです。
社葬の流れと準備
社葬は通常、葬儀会社と綿密に打ち合わせを重ねながら、1ヶ月程度かけて準備されることが多いです。
社葬の主な流れ
- 訃報の社内外通知
- 社葬実行委員会の立ち上げ
- 会場・式の形式の決定(宗教儀礼の有無)
- 招待者リストの作成・案内状発送
- 受付・式次第・返礼品の準備
- 式の進行(弔辞・献花など)
- 会計報告・香典管理・社内報告
社葬にかかる費用の目安
社葬の規模によって異なりますが、数百万円〜1,000万円以上になるケースもあります。
- 式場使用料・祭壇費用
- 返礼品・お食事代
- 招待者交通費・宿泊費
- 案内状や式次第の印刷費用
- 演出(音響・映像・司会) など
社葬を行う上での注意点
法的手続き・税務処理
社葬費用のうち、業務関連性が認められる範囲は損金(経費)として処理できます。
ただし、税務署への説明責任もあるため、領収書や明細の保管は厳重に行いましょう。
ご遺族との連携
社葬は企業主催とはいえ、遺族の意向を無視してはいけません。
日程・形式・弔辞内容など、あらかじめ合意を得た上で進めることが重要です。
社葬の実績豊富な当社にご相談ください
ライフサポートでは、社葬・合同葬・団体葬の実績が多数ございます。
宗教儀礼の有無や無宗教形式、規模の大小を問わず対応可能です。
まとめ:社葬は企業の姿勢を表す大切な儀式
社葬は単なる葬儀ではなく、会社の理念や価値観を対外的に示す儀式でもあります。
丁寧に計画し、故人の功績にふさわしい場を設けることが大切です。
社葬をご検討中の方は、ぜひ当社までご相談ください。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
株式会社ライフサポート|公営斎場専門の葬儀社(千葉県・茨城県・埼玉県)
大切な方とのお別れを、心を込めてお手伝いいたします。
ライフサポート株式会社
柏市布施281-1
フリーダイヤル:0120-873-444
公式ホームページはこちら
大切な「その時」のために、後悔のない準備を。ライフサポートは皆様の安心をお手伝いします。