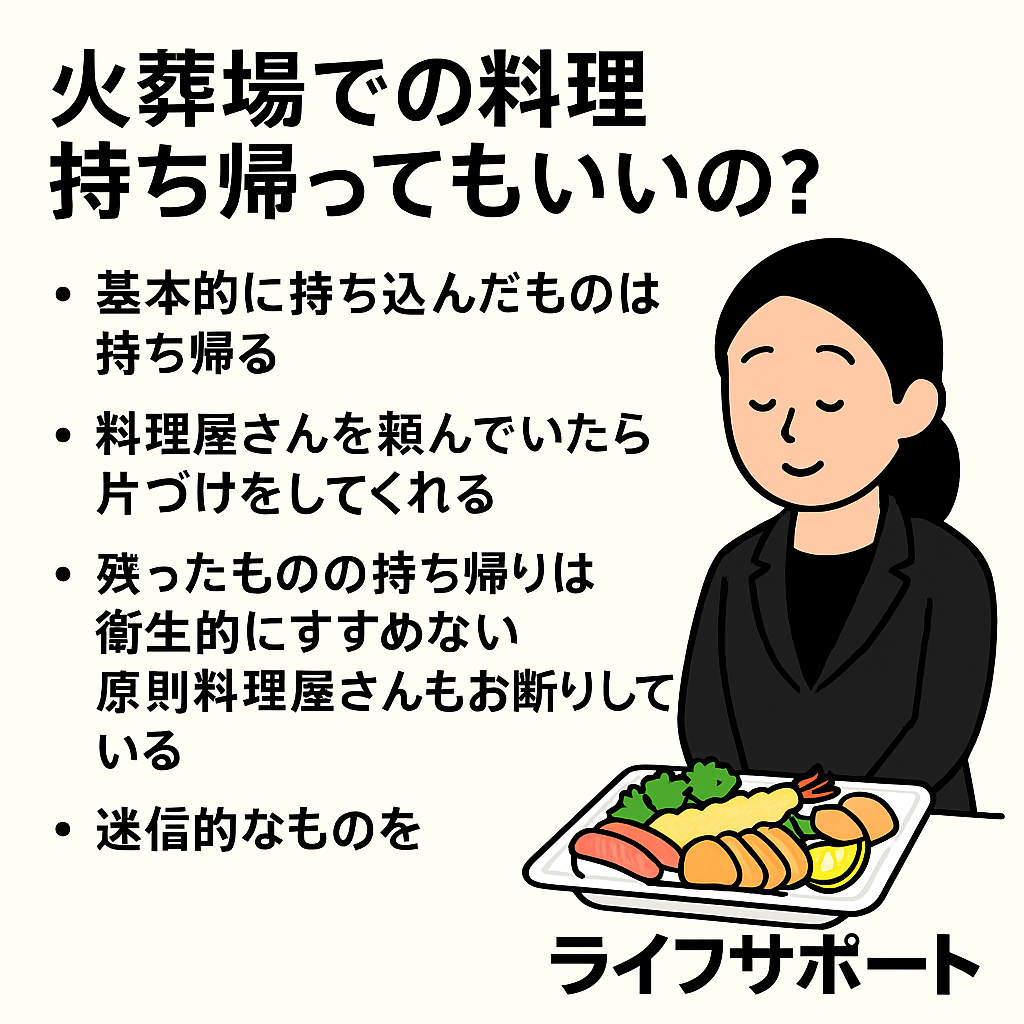「死亡届を出すとすぐに銀行口座が凍結されるって本当?」「葬儀費用が出せなくなったらどうすればいい?」
ご家族が亡くなられた際、多くの方が疑問に感じるこのテーマについて、実際の流れと注意点を分かりやすく解説します。
■ 死亡届と銀行口座の凍結は別の話です
死亡届は、市区町村役場に提出される公的な手続きです。
ただし、この情報が自動的に銀行へ伝わることはありません。
銀行口座が凍結されるのは、金融機関がご本人の死亡を知った時点です。
たとえば、家族や知人が銀行へ「亡くなったので解約したい」と連絡した際や、新聞の訃報、公的な通知が届いた場合などに口座は凍結されます。
■ 口座が凍結されるとどうなる?
- 預金の引き出しや振り込みができなくなる
- 公共料金などの自動引き落としも停止される
- 相続手続きが完了するまで口座は動かせない
一部のご遺族が勝手に引き出すと相続トラブルの原因にもなり得ます。
故人の資産管理には慎重な対応が必要です。
■ 凍結前に葬儀費用を引き出すのはOK?
口座凍結前であれば、ご家族が必要な費用を引き出すこと自体は違法ではありません。
ただし、他の相続人との関係性や今後の手続きも考慮して、可能であれば事前に相談・共有するのが望ましいです。
最近では、葬儀費用だけを対象にした払い出し制度を設けている金融機関もあります。
■ 相続や名義変更が不安な方へ|当社のアウターサポート
当社ライフサポートでは、葬儀後のご不安を軽減するために「アウターサポート部」を設置し、相続や不動産名義変更などのご相談にも対応しています。
また、司法書士・行政書士などの専門家のご紹介も可能です。
いずれもリーズナブルな価格で誠実な対応を行う提携士業ですので、安心してご依頼いただけます。
相続放棄・不動産処分・遺言書の検認など、状況に応じた対応が必要な手続きもございますので、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
■ まとめ|口座凍結を知っていれば安心
銀行口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されるという点をまず理解しておくことが大切です。
また、相続手続きには多くの書類や段取りが必要となるため、信頼できるプロに早めに相談しておくことで、余計なトラブルを回避できます。
葬儀からその後の手続きまで、トータルでサポートしているライフサポートに、ぜひご相談ください。
📞 ライフサポート フリーダイヤル:
0120-873-444(24時間 年中無休)
🔗 公式サイト: https://anshin-sougi.jp/