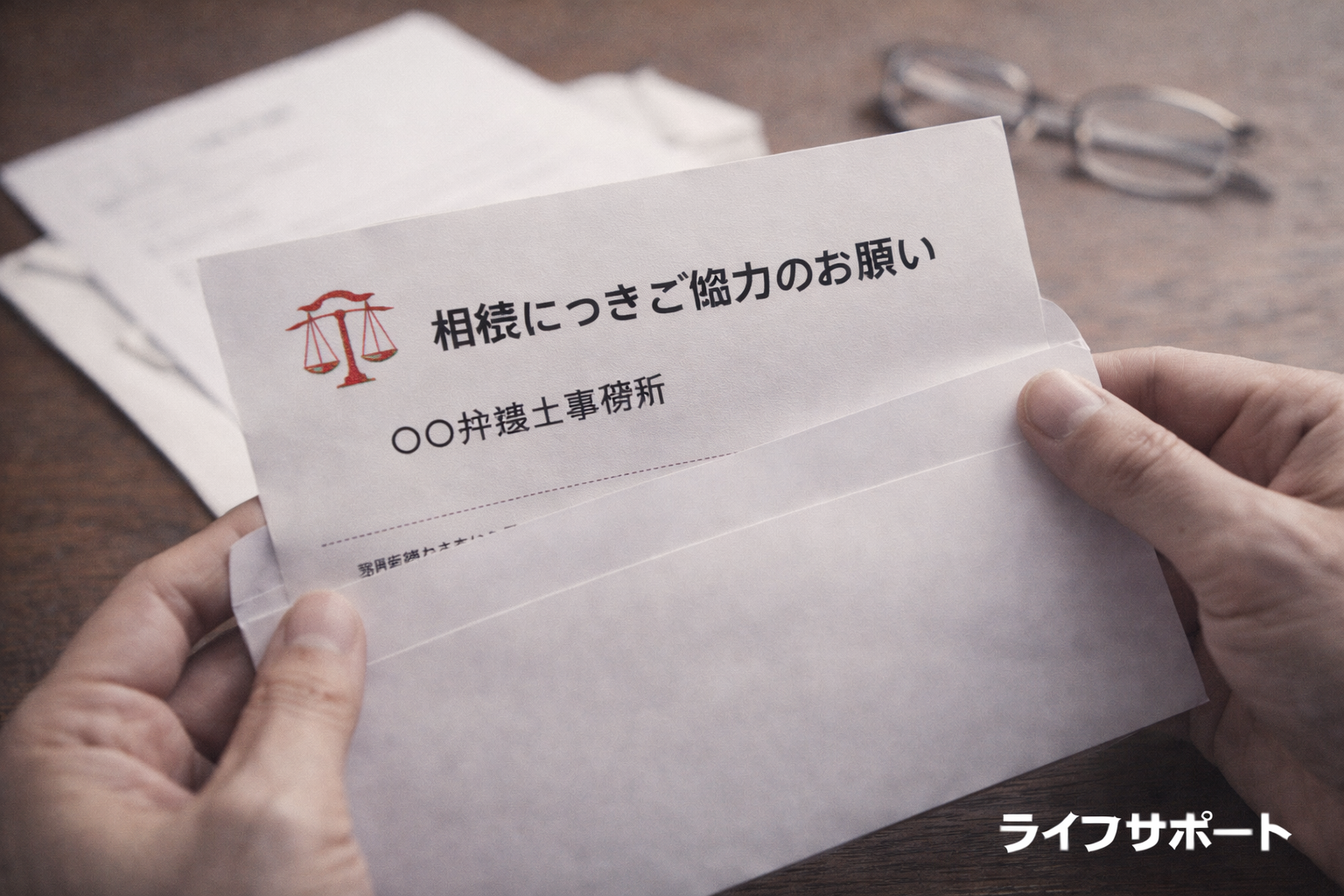近年、単身世帯が増えています。
その中でよくいただくご相談が、
「もし一人で亡くなったら、ペットはどうなるの?」
というものです。
大切な家族だからこそ、
気になる方も多いと思います。
今回は実際の流れを、葬儀社の立場からわかりやすく解説します。
飼い主が亡くなった直後、ペットはどうなる?
まず、亡くなられた状況によって対応が変わります。
自宅で発見された場合
警察や救急が入るケースでは、
- 室内にペットがいることが確認される
- 親族へ連絡が行われる
ことが一般的です。
ただし、すぐに引き取り先が決まらない場合もあります。
誰がペットを引き取るの?
多くの場合は次の順番になります。
① ご家族・親族
まずは親族へ確認されます。
② 知人・近隣・知り合い
生前に関係があった方へ相談されるケースもあります。
③ 保健所・行政
引き取り手がいない場合、
自治体が一時保護することがあります。
ただし、必ずしも長期保護できるとは限りません。
実際に多い問題
葬儀の現場では、
- ペットが数日間発見されない
- 食事がなく弱ってしまう
- 引き取り先が決まらない
というケースもあります。
だからこそ、
生前の準備がとても重要になります。
今からできるペットのための備え
おすすめなのは次の3つです。
✔ 引き取りをお願いする人を決めておく
口約束ではなく、家族や友人と話しておくこと。
✔ メモを残しておく
玄関や財布に
- ペットがいること
- 連絡先
を書いておくだけでも違います。
✔ エンディングノートに記載
最近は
- ペット情報
- かかりつけ病院
- 性格や注意点
を書き残す方が増えています。
葬儀社として感じること
一人暮らしの方ほど、
「自分よりペットが心配」
と話されます。
実際、
ペットの行き先が決まっていると、ご家族も安心されます。
これは終活の大切な一部です。
まとめ|ペットも“残される家族”
- 一人世帯ではペット問題が増えている
- 引き取り先が決まらないケースもある
- 生前準備が最大の安心につながる
大切なペットが困らないために、
少しだけ準備をしておくことをおすすめします。
ご相談・お問い合わせ
終活や事前相談についても、
どうぞお気軽にご相談ください。
株式会社ライフサポート
📞 0120-873-444(24時間受付)
🌐 https://anshin-sougi.jp/