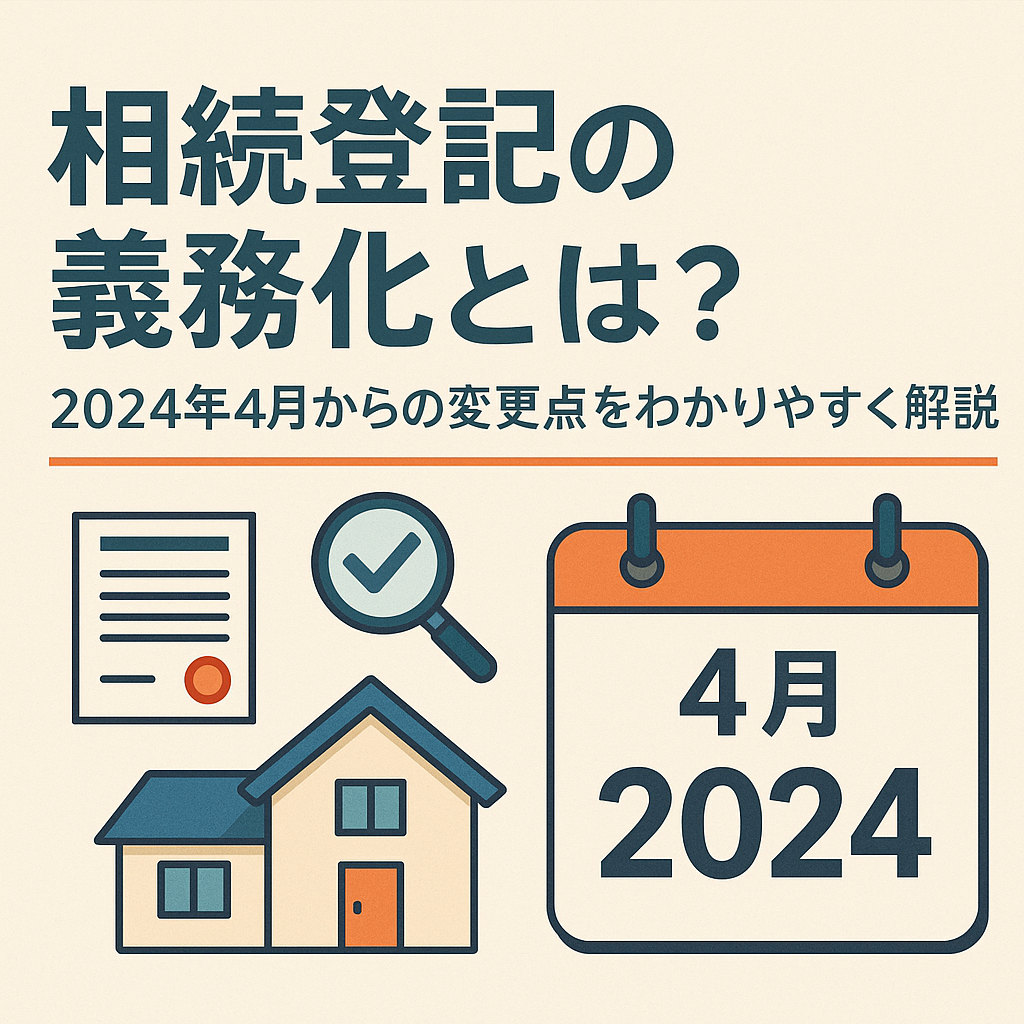はじめに
「相続登記」という言葉を聞いたことはあっても、「義務化」という言葉とセットで聞くケースはこれまで少なかったかもしれません。2024年4月から、相続登記が法律上の義務となる改正が施行されます。本記事では、改正の背景から具体的なルール・罰則、注意点・実務の流れまでを分かりやすく整理して解説します。
1. 相続登記の義務化とは?改正の背景
1.1 相続登記とは
相続登記とは、故人から不動産を引き継ぐ際に、法務局で名義を変更する登記のことです。
これまで、この登記は任意であり、相続人が行わないケースも多くありました。
1.2 なぜ義務化されたのか?
主な理由は 所有者不明土地 の増加問題です。登記簿上、誰が所有者かわからない土地が増えると、公共事業やインフラ整備、地域開発などに支障が出るからです。
そのため、国の政策として、相続登記の促進を図る必要があると判断され、法制度が見直されました。
2. 義務化の具体的なルール(2024年4月以降)
2.1 施行日と適用範囲
- 義務化の開始:令和6年4月1日(2024年4月1日)
- 施行前の相続も対象:2024年4月1日以前に相続が開始した不動産についても、義務化の対象となります(ただし猶予期間あり)
2.2 登記すべき期限
改正後、新たに不動産を相続した(または相続で取得したことを知った)人は、3年以内 に相続登記を申請しなければなりません。
また、遺産分割協議を経て不動産を取得する場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記をする必要があります。
ただし、2024年4月1日より前に発生した相続については、 令和9年3月31日 までが期限(猶予期間)と定められています。
2.3 過料(罰則)
正当な理由なく、登記申請を怠った場合には 10万円以下の過料 が科される可能性があります。
ただし、まず登記官から催告(登記を促す通知)があり、それに応じない場合に裁判所を通じて過料が課されるという流れです。
正当な理由が認められる事情としては、戸籍収集や相続人の把握が著しく困難な場合、遺言の有効性が争われている場合、本人が病気で手続きができない場合などが挙げられます。
3. 新設された制度・改正点(義務化に伴う周辺ルール)
3.1 相続人申告登記(新制度)
義務化に合わせて「相続人申告登記」という制度が創設されました。
これは、遺産分割がまだ確定しない場合など、簡易な形で相続の事実や相続人を法務局に申し出ておく制度です。手続きを怠らないことで、義務を履行したとみなされる場合があります。
ただし、この申告登記のみでは不動産の売却や抵当権設定には対応できない点に注意が必要です。
3.2 遺贈による登記の簡素化
遺贈(故人が指定した第三者に財産を譲ること)で不動産を取得した場合、改正によって 受遺者が単独で所有権移転登記を申請できるように なりました。
3.3 その他の関連制度
- 相続土地国庫帰属制度:相続したものの利用価値が低い土地などを、一定の条件のもとで国に帰属させる制度(2023年4月に施行)
- 住所変更登記義務化(予定):将来的には、不動産名義人の住所変更手続きも義務化される見込みが報じられています。
4. 義務化後に相続登記を行うときの流れと必要書類
以下は、一般的な流れと主な必要書類(目安)です。ただし、事案の内容によって異なるため、専門家(司法書士など)に確認することをおすすめします。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 相続関係の把握 | 戸籍(除籍・改製原戸籍など)、住民票、登記事項証明書などを取得 |
| 相続人の確定・遺産分割協議 | 相続人全員で話し合い、合意を得る/遺言があれば内容に従う |
| 必要書類の準備 | 被相続人の除籍謄本・住民票除票・固定資産評価証明書・相続人の戸籍・住民票 等 |
| 登記申請 | 管轄の法務局に申請(あるいはオンライン申請) |
| 登記完了 | 名義変更が登記簿に反映される |
主な必要書類例:
- 被相続人の戸籍・除籍謄本、戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 固定資産評価証明書(登記のための基礎資料)
- 遺産分割協議書(協議による場合)
- 遺言書(遺言がある場合)
- 相続人申告登記申請書(必要に応じて)
なお、法務省の「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」では、各種様式や手順も詳細に案内されています。法務局
5. 義務化を放置するとどうなる?リスクと注意点
- 過料のリスク
前述のとおり、10万円以下の過料が科される可能性があります。 - 不動産取引・融資・抵当権設定の障壁
名義が旧のままでは、不動産を売却したり担保に入れたりする際に手続き上の不備が生じやすくなります。 - 所有者不明土地の増加・行政手続きの遅れ
登記簿に所有者情報がない、あるいは古いままだと、公共事業や地方自治体が土地を活用する際に障害になる可能性があります。 - 相続人間でもめやすくなる
相続関係が複雑な場合、長期放置することで相続人同士の主張がぶつかり、処理が難航する恐れがあります。
6. 義務化にあたってのポイント・対策
- 早めに相続関係を整理する
不動産を持っていた親が亡くなった場合は、まず戸籍調査・相続人確定を始めましょう。 - 遺産分割を可能な限り早く進める
遺産分割が確定すれば、正式な相続登記がスムーズにできます。 - 相続人申告登記を活用する
分割が難航しているケースでも、とりあえず申告登記をして義務を履行しておく選択肢があります。 - 専門家(司法書士)を活用する
書類収集や書き方、手続きの順序など、専門家に依頼することでミスを防ぎ、時間も節約できます。 - 将来制度の動向にも注意
住所変更登記義務化など、今後も登記制度に関する法改正が予定されているため、最新情報をチェックしましょう。
まとめ
2024年4月から相続登記が義務化される改正は、不動産を所有する多くの人に影響を与える大きな変化です。義務化の対象となる相続・不動産、申請期限、罰則、そして新設された制度(相続人申告登記など)を正しく理解し、早めの対応を心がけることが肝要です。
📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
株式会社ライフサポート|公営斎場専門の葬儀社(千葉県・茨城県・埼玉県)
大切な「その時」のために、後悔のない準備を。ライフサポートは皆様の安心をお手伝いします。